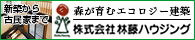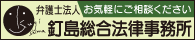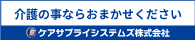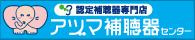本文
令和7年6月教育委員会会議定例会の会議録
1 期日
令和7年6月20日(金曜日)
2 場所
県庁24階 教育委員会会議室
3 出席者
平田郁美教育長、河添和子教育長職務代理者、日置英彰委員、小島秀薫委員、中澤由梨委員、宮坂あつこ委員
4 事務局出席者
高橋正也教育次長、古市功教育次長(指導担当)、西村琢巳総合教育センター所長、小林謙五総務課長、角田毅弘管理課長、酒井隆福利課長、角田義行学校人事課長、佐野美幸義務教育課長、高橋章高校教育課長、池田克弘特別支援教育課長、都丸要生涯学習課長、山田知利健康体育課長、鈴木智行総務課学びのイノベーション戦略室長、箱田陽子生涯学習課社会教育主監、高井俊一総務課次長、代田英敏総務課補佐(行政係長)、高田和樹総務課主幹
5 開会
午後1時00分、平田教育長、教育委員会会議の開会を宣す。
傍聴人は1名、取材者は3名であることを報告。
6 会議録署名人の指名
平田教育長が今回の会議の会議録署名人に宮坂委員を指名。
7 議案審議等の一部を非公開で行うことについて
議案審議に先立ち、平田教育長から、第20号議案から第22号議案は附属機関の委員の委嘱に関する案件であるため、第23号議案は教職員の人事に関する案件であるため、審議は非公開で行いたい旨の発議があり、全員賛成で議決した。
8 教育委員会の行事日程
教育委員会の主要行事日程及び次回定例会議の日程について、総務課長が説明。
9 教育長事務報告
(平田教育長)
始めに私から一言申し上げる。
はじめに、まだ梅雨明け前の時期ではあるが、今年は、まるで夏本番のような気温の高い日が続いている。さらに、今年の夏は全国的にも気温が高くなることが予想されている。こうした中で、子どもたち、教職員、また学校に関わる方々の熱中症などによる健康リスクが心配される。
県教育委員会としては、児童・生徒、さらには教職員の皆さん、また関わってくださる皆さんが、学校において、安心して学び、働くことができるよう、気温が高い状況下での活動への配慮や、空調の適切な利用など、今後も熱中症の予防等に努めてまいりたい。
続きまして、令和7年第2回定例県議会が5月22日から6月13日までの会期で開催された。
一般質問では、「県立高校の未来像」についての質問があったほか、「インクルーシブ教育」に関して「モデル校での取り組み」と、「高校通級における現状と課題」について質問がなされた。
このほかにも、「県立学校の体育館の空調設備の整備」、「高校教員の定数」、「朝のこどもの居場所づくりにおける学校施設の活用」などの質問があった。
また、文教警察常任委員会では、『新・沼田高校』について、「開校後の状況や生徒の様子」についての質問があったほか、『保護者が学校へ提出する書類のデジタル化』、さらには、新たに導入した『Web出願』の実施状況についての質問などをいただいた。
さらに、今回の定例会では、新たに4つの「特別委員会」が設置された。
教育委員会の関係では、「防災・減災・治安に関する特別委員会」と「スポーツ・文化に関する特別委員会」の2つの特別委員会に関係課が出席している。
このほか、前回の定例会において、承認いただいた「教育委員会関係の補正予算」、「伊勢崎特別支援学校の整備」の議案については、いずれも原案どおり可決された。
私からは以上である。
それでは、各教育委員から意見や報告をお願いする。
(河添委員)
私は、6月9日の教育委員と教育事務所長との意見交換会に参加をさせていただいた。
教育ビジョンの1年目における非認知能力育成に向けた取り組みをテーマに、各事務所からの状況や課題等も話し合われ、大変貴重な機会となった。
私は昨年8月に開催された、1都9県教育委員会教育委員協議会で、「認知能力と非認知能力をバランスよく育むために」というテーマを提案させていただいた。その協議の経験を元に、今回はバランスの大切さについても、所長や皆さんと協議できたことを大変うれしく思っている。
中でも、教育は見かけや形ではなく、子どもたちがどのように自ら主体となり、学ぶ日々を過ごせるかが大切であると感じている。例えば、一斉と自由進度、教師主導や児童生徒主体、知識スキルと思考判断等々のニ項対立ではなく、確かな学力等の基礎的基本的事項を育成する資質能力と主体的な学びは、エージェンシーで繋がっていると感じているので、形態だけではなく、子どもの姿が第一だと思っている。
そのため、教職員が子どもたちの状況に応じて、主体的に取り組む授業や、良さや特性を引き出すための土台となる日々の言葉かけや、児童・生徒理解や発達指示的な生徒指導、心理的安全性のある学級づくりや、関わりづくりなど、地道であるが、とても大切な部分にも光を当てた取り組みや実践を大切にした、群馬の先進的なモデルが出来てくると良いということを発言させていただいた。
指導方針や伝達事項等の発信を続けていくことも必要であるが、ある程度、先生方が状況に合わせて工夫している姿を信じて任せていくことも、大切だと思っている。
教員にも子どもにも理解しやすく、日々の取り組みにも光を当てていただける、肯定感のあるモデルが出来てくるといいと感じて、この会に参加をさせていただいた。
群馬県は勿論間違ったメッセージになっていないが、昨年9月の次期学習指導要領に向けた文科省の論点整理の中で示された、「教師は教えなくてもよい」、「子供に委ねればよい」といった、間違ったメッセージにならないようにという例も、以前話させていただいたことと繋がっている。
また、6月13日に群馬大学共同教育学部附属小学校の公開研究会に参加した。
講演会では、京都大学の石井准教授の貴重なお話を聞くことが出来たので報告したい。
石井先生は、文科省の委員としても活躍をされているが、先ほどの文科省の論点整理と同様な話をされていた。
「授業は、教えることと、学び合いの絡み合い。二項対立でなく、教えることや、教師の仕事がなくなることはない。子ども、教材、教え方、どれも大切である。やり方でなく、子どもと内容、児童理解、内容理解が大切。一人一人を丁寧に出来る教師の力をセットで考えていく。しっかりと教師の指導性にも光を当てていくこと。学級が安心安全で、自分らしさを出せる、学級づくりも大切である。新しい取り組みでキラキラした学校ではなく、地味でもいいので、地味にいい学校を作る。」
そのようなお話をされ、学習指導要領の改訂や、今後の群馬モデルにも繋がる貴重なお話であると思ったので、報告をさせていただいた。
研究会もよい話し合いが展開されており、貴重な機会をいただいた。
(日置委員)
私も6月9日教育事務所長との意見交換会に参加させていただいた。
新しい教育ビジョンがスタートして1年目ということで、各事務所で非常に積極的に、校内研修や計画訪問などを行っており、子どもたちが自分で考えて、自分で決めて、自分で動くという、教育長の考え方は各学校にしっかりと伝わってるということを感じた。
ただ一方で、この考えを授業に、どのように落とし込んでいくかということに関して、先生方の計画に温度差があるという報告もあった。
生徒がエージェンシーを発揮する場面を、教育課程のどこで、どのように育成するのか、認知能力と非認知能力のバランスを、どのように図っていくのかということに関して、教師のエージェンシーが一番出しやすいところであり、先生方が悩んでる部分でもあると思う。
既に1年目から、具体的な例を出されている事務所もあったが、そういう例がたくさん出てくると、それらを参考にしながら、先生方が自分で、この場面でというようなことが出てくるのではないかと思う。
それから、この会議の中で中澤委員が指摘したことに関連するが、非認知能力は、極めて内面的なもので、その性質と非常に密接な関係がある。例えば、アントレプレナーシップをすべての子ども達が育んだら良いのかというと、そうではないのではないか。
非認知能力を自分がどう伸ばしたいかということについても、自分で考え、自分で決めて、それを行動に移すということも、とても大切なのではないかと思っていたところである。
(小島委員)
私も6月9日の教育事務所長との意見交換会に出席させていただいた。
新しい教育ビジョンの教育の仕方が、有り難いことに着実に進んでいるという印象を受けた。
最近の企業の例だが、新入社員の中には、退社するにあたって代行業に頼む人がいる。引き止められるのが嫌なのか、面倒なことを自分でやりたがらないのか、といういうことかと考える。入社時からすると、その数年前に「教育」を受けているわけだが、どういった教育で、それがどう影響を及ぼして、こういった社員が出てくるのかという見方をしている。
今回の教育ビジョンが始まり、授業で行われていることが、就職の時にどういう形で反映されてくるのかと考える。
会議の中でも話しをしたが、今の教育ビジョンの中の、皆と仲良くやっていく協調性という能力は、会社の中で一番幸せに暮らせる方法なではという感じがする。
ただ、そういったことが苦手な人もいるわけで、そういう人をどう使うかという意味では、その教育を受けた人よりも、むしろその教育を受けて就職してきた人を受け持つ社員に教育をしたいところである。
自分は公務員も民間の経験もあるが、公務員と違い、民間は、入社した人は出来るだけ、自分の会社にいてもらい、役に立ってもらいたいということがベースになる。
周りの人と合わない社員に対する対応や、指導が出来る社員を教育することも大事かな、と思う。自分も含めどう教育をすれば良いのかと思いながら参加した。
(中澤委員)
6月9日の教育事務所長との意見交換会について、話させていただく。
教育ビジョンの成果と課題ということで、特に「非認知能力を育むための具体的な取り組み」について、聞かせていただいた。
教育ビジョンについては、日置委員からも話があったが、この1年で、教育事務所長をはじめ、教育事務所の皆さんが、地域に出向き、たくさん意見交換などを行う中で、その手応えを感じているということがとても印象に残った。今後、さらに具体的な取り組みに繋げていきたいということであったと思う。
私も非認知能力について日頃から感じていることであるが、小島委員が言うように、企業に入り働いていくときに、自分のことを大事にして、自分を調整して、どう調整しながら他の人と一緒にやっていくのかという社会情動性のスキルが、とても大事になってくると思う。
それをどうやって伸ばすかということを、各教育事務所の皆さんが考えてくださっていた。例えば、異学年交流を行なったり、川場小の例では、自分で目標を立て、どのような活動で、どのような人になりたいかという、自分で立てた目標に対して努力するという取り組みをしていた。非常に大事なことだと思った。
私は日頃から自分が自分を理解し、どういう人間になっていきたいかということを考えていくことが、一番大事だと思っている。それは他人から「こういう人がいいよ」とか、「こういうふうになると社会に出て役に立つ」と言われるよりも、自分がなりたいものはどうかということの方が、自分を伸ばす可能性があり、大事だと思う。自分のパーソナリティや、自分のキャラクター、自分の価値を大事にしていくことで、その非認知能力が伸びていくのではないかと、今回の取り組みを聞く中で感じた。
この自己調整や情動調整は、いろいろな要因によって苦手な子ども達もいるが、先生達が一人一人に「こっちのやり方のほうが君はやりやすいね」と伝えるなど、先生や大人の手助けがあると、その子ども達が道を見つけやすくなると思う。
そういった先生が一人一人を見るという、川添委員のお話しにあった、一番基本となる地道な取り組みが、非認知能力を伸ばしていくすべてに繋がるのではないかということを感じる会議だった。
(宮坂委員)
皆さんと同じく、6月9日の「教育事務所長との意見交換会」に参加させていただいた。
教育ビジョンの非認知能力について、各地区の取り組みは本当に素晴らしく、浸透されており、子ども達のことを考えてくれていると、本当に嬉しく、ありがたいという気持ちである。
親として、先生方が一生懸命にやってくれて、考えているということを、どう親たちに伝えられるのかを、いつも考えてる。
非認知能力を伸ばすということは、良くなろうとする力をつぶさず、伸ばす。つぶさなければ、伸びる可能性がある。
そこに先生方のお力で、さらに覚醒させ、芽吹かせていけるような、そのような環境になっていく兆しが見える会議であり、嬉しさを感じた。
特別支援教育は、まさに個別に能力を伸ばす、その子の良さをどう活かしていこうかという教育であると思うので、やはり最先端の教育ではないかと改めて思った。
(平田教育長)
教育事務所長との意見交換会では、貴重な意見をいただき、感謝する。
それでは、関係所属長から報告をお願いする。ご質問はすべての報告が終了した後、一括して行う。
(1)令和8年度採用公立学校教員選考試験応募状況について
学校人事課長、資料1 (PDF:58KB)により報告。
(2)令和7年度「全国学力・学習状況調査」児童生徒向け学習サポート動画について
義務教育課長、資料2 (PDF:1.33MB)により報告。
(3)令和7年度「いじめ防止フォーラム」の実施について
義務教育課長、資料3 (PDF:70KB)により報告。
(平田教育長)
ただいまの報告について、委員から意見や質問があるか。
(河添委員)
先ほどの、児童生徒向けの学習サポート動画について、長さも5分程度のものが何本もあるということで、ぜひ全部を活用していきたい。
公開してくださっているのは非常にありがたいが、配信期間が2ヶ月では短いので、長くしていただくと良いかと思う。研修会でワンポイントを取り上げて見ていただければ、後で全部を見ようとなる。1年を振り返って、見ることも出来ると思う。
(義務教育課長)
配信期間は区切っていない。
配信を開始するのが、調査終了から2ヶ月後になる。動画は令和4年度に作成したものも見られるので、長期間見られるようになっている。
過去の配信も見られること等を含め、周知をしていきたい
(平田教育長)
ご指摘いただいて、この説明が分かりづらいかもしれないので、発表するときに分かりやすい文書に改善するよう検討した方が良い。
(日置委員)
サポート動画について、昨日少し見たが、今年から理科はCBTになっており、内容を見ても、まさに今の探究的な問題となっている。「この問題について課題を立てなさい」とか、「終わった後の振り返りや考察を書きなさい」等。それを動画で、また顕微鏡で見た写真などもあり、まさに今やってる授業を再現しているようなストーリーがあるので、子ども達の振り返りに活用できる。例年のように先生への説明もあるのか。
(義務教育課長)
はい。先生には、説明会で説明する。
(日置委員)
理科は3年ぶりであったが、3年前から見ても、本当に今の教育ビジョンに合っているので、ぜひ先生に見ていただいきたい。先生にとって勉強になる、とてもいい動画だと感じた。
もう1点、採用試験について教えていただきたい。
今年初めて大学3年生通過者が受験する。昨年度通過者の86%が今年度受験すると聞いたが、受験しない30人弱は他県を受検たり、大学推薦へ移ったということが考えられるが、このことについて分析しているか。
(学校人事課長)
詳しく分析していないが、通過しているにも関わらず、大学等推薦に回った受験者もいる。
(日置委員)
それがどのぐらいいるのかを知りたい。
他県出身者で、3年生で他県での資格を取ったが、4年生になって、大学推薦があるし、やはり群馬県で受験すると考え、結局3年生での資格を辞めて、群馬県を受験してくれるという人もいるのではないか。
だから、その動向がこの大学3年生の通過者と、逆に他県の3年生通過者でありながら、大学推薦で受けている例があるので、その辺りの動向知りたい。それから、もう1つは3年生を対象とする選考がかなり増えたということだが、これをどのように捉えるかということが、今後の教員の宣伝や広告する際のヒントになるのではと思う。
(学校人事課長)
昨年の通過者が173名で、今回の試験では173人のうちの149人が応募した。
群馬県の通過者が、群馬県の大学推薦に回った受験者が若干名おり、他県からの受験県替えついては分からない。
また、今年度の大学3年生は383名と大幅な増加となったことは、様々な機会に伝えいたい。
(日置委員)
大学3年生の通過者は、他県と迷ってるという例がある。おそらく、大学推薦が取れそうだと思ったり、2つを天秤にかけて最後に決めているという人も一定数いると思う。
その動向と同時に、今3年生で受験する人は、昨年から始めたのに群馬県が100人も増えたということを、どう解釈したらいいのか。
(学校人事課長)
自己アピール用紙をなくした。そのため、応募しやすくなったのも要因ではないかと感じている。
(日置委員)
今まで応募がなかった大学が増えたとか、そういった傾向があるか。
(学校人事課長)
受験のあった大学等については、今後分析をしていきたい。
(平田教育長)
だから、我々が今後考えなければいけないのは、倍率を上げるということを目指すのではなく、いかに優秀な人に、いかにやる気のある人に、群馬県を受験していただくかというところに注目していかなければいけないと思う。
「こういう自分の良いところを見てくれるなら群馬県ぜひ受けたい」と思う学生を増やしていくために、選考の方法を考えていくことがとても大事である。
(日置委員)
やはり、教員に興味を持ってもらうということと、群馬県に興味を持ってもらうというところで、分析する必要があると思った。
(平田教育長)
教員の働き方改革が進んで、先生方がやる気を持って、心身のゆとりを持って、やりがいを持って働ける環境を作っていくこと。 そうすると、そういった先生を見た中学生あるいは小学生、高校生が自分も先生になりたいと思う。
教員は多忙ではあるが、教員の素敵さを発信していくという、その両面からやっていかなければならない。これは、教員養成をしている大学とも、連携してやっていかなければならないことだと思う。
(中澤委員)
いじめ防止フォーラムについて、甘楽富岡地区がオンライン開催となった背景などありましたら、教えていただきたい。
(高校教育課長)
おそらく、コロナ禍がきっかけかと思う。
この事業は、平成25年度から始まり、今回で13回目になる。非常に歴史のある、全国的にも珍しい事業である。
コロナが感染拡大していた時期には中止していたこともあったが、オンラインで集まることが出来るなら、実施したほうが良いということになった。
オンラインでの開催の場合は、多くの学校が集まれるというメリットがある。
ハイブリッドという形など、色々な形で、子ども達がしっかりと話が出来るような環境を考えた。
(中澤委員)
コロナ禍でも持続して開催されていたとのことであり、とても意義のあることであったと思う。
オンライン開催のメリットと対面開催のメリットを教えていただきたい。
(平田教育長)
コロナが、五類になってから、時間が経つ。オンラインでやったほうがより良いのか、それともハイブリッドがいいのか、あるいは対面が良いかということについても、おそらく知見がたまっていると思う。
甘楽富岡地区が今もオンラインでやってるということは、強い思いがあるのかと思う。義務教育課と高校教育課の両課でどのような理由があるのかということも含め、オンラインと対面のそれぞれの良さ等をまとめて、中澤委員へ回答していただきたい。
これは、高校生にとっても、ものすごく学びの機会になる。
高校生がリードをして、そして中学生もサブリーダーとして手伝い、特別支援学校、小学校の子どもと話し合いをする。
そして、それぞれの子どもが学校に戻って、今度はその子ども達がリーダーとなって、各学校で話し合うという、とても良い取り組みである。
だからこそ、できるだけ効果の高い方法が大事となるので、状況を調べていただければありがたい。
ほかになければ、以上で、教育長事務報告を終了する。
10 議案審議
第19号議案 令和8年度群馬県立高等学校生徒募集定員について
高校教育課長、第19号議案原案 (PDF:229KB)について説明
異議なく、原案のとおり決定
11 議案審議(非公開)
ここで、平田教育長から、これからの審議は非公開で行う旨の発言があり、傍聴人及び取材者は退室した。
第20号議案 群馬県立図書館協議会委員の任命等について
生涯学習課長、第20号議案原案について説明
異議なく、原案のとおり決定
第21号議案 群馬県社会教育委員の委嘱について
生涯学習課長、第21号議案原案について説明
異議なく、原案のとおり決定
第22号議案 群馬県学校保健審議会委員の委嘱について
健康体育課長、第22号議案原案について説明
異議なく、原案のとおり決定
第23号議案 教職員の人事について
高校教育課長、第23号議案原案について説明
異議なく、原案のとおり決定
12 教育委員会記者会見資料について
教育委員会記者会見資料について、総務課長が説明。
13 閉会
午後2時07分、平田教育長、教育委員会会議の閉会を宣す。