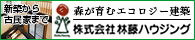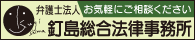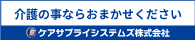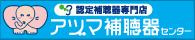本文
令和7年7月教育委員会会議定例会の会議録
1 期日
令和7年7月22日(火曜日)
2 場所
県庁24階 教育委員会会議室
3 出席者
平田郁美教育長、河添和子教育長職務代理者、日置英彰委員、小島秀薫委員、中澤由梨委員
4 事務局出席者
高橋正也教育次長、古市功教育次長(指導担当)、西村琢巳総合教育センター所長、小林謙五総務課長、角田毅弘管理課長、酒井隆福利課長、角田義行学校人事課長、高橋章高校教育課長、池田克弘特別支援教育課長、都丸要生涯学習課長、山田知利健康体育課長、鈴木智行総務課学びのイノベーション戦略室長、箱田陽子生涯学習課社会教育主監、高井俊一総務課次長、藤村正博義務教育課次長、代田英敏総務課補佐(行政係長)、高田和樹総務課主幹
5 開会
午後1時00分、平田教育長、教育委員会会議の開会を宣す。
傍聴人は2名、取材者は3名であることを報告。
6 委員の欠席届について
平田教育長が、宮坂委員から欠席の届出があったことを報告。
7 会議録署名人の指名
平田教育長が今回の会議の会議録署名人に日置委員を指名。
8 教育委員会の行事日程
次回定例会議の日程について、総務課長が説明。
9 議案審議等の一部を非公開で行うことについて
議案審議に先立ち、平田教育長から、第24号議案は附属機関の委員の任命に関する案件であるため、第25号議案から第28号議案は教職員の人事に関する案件であるため、審議は非公開で行いたい旨の発議があり、全員賛成で議決した。
10 教育長事務報告
(平田教育長)
始めに私から一言申し上げる。
はじめに学校訪問について、報告させていただく。
7月4日に教育委員の皆様と学校訪問を実施した。
今回は、義務教育学校として新たに開校した「川場村立川場学園」と、沼田高校と沼田女子高校が統合し、新たに開校した「沼田高校」を訪問した。
「川場学園」では、子ども達が地域の皆さんに見守られながら、 新たに開校した学びの場で生き生きと学習に励む姿や、学年の枠を超えて清掃活動する姿などを拝見することができた。
次に「新・沼田高校」では、生徒会の皆さんとの意見交換を行う機会があった。生徒会の皆さんからは、統合前に行った新高校の制服デザインの検討や、新たなルール作りを行った際に苦労したこと、さらには、統合後の新高校の感想などについてお聞きした。
この他、生徒が設定したテーマについて探求する「探求授業」を見学させていただいたが、生徒の皆さんが意欲的に授業に取り組んでいる様子を拝見することができた。
加えて、インクルーシブ教育の専門委員会を設置しており、委員の皆様方と、玉村町立上陽小学校を拝見して参った。
障害のあるなし、日本語が使える使えない、あるいは様々な生きづらさを抱えている、抱えないなど、様々な子どもが、それぞれ自分の居場所があるように、教室のあり方であったり、あるいはクラスの持ち方であったり、授業の行い方であったり、様々な工夫がされていた。インクルーシブ教育の構築のみならず、群馬教育ビジョンで私たちが目指している、全ての子どもたちが主役となるような、そういった学校づくりに直結する取り組みだと感じた。
次に、県立高校の生徒の活躍についてお話をさせていただく。
4月に行われた「国際親善空手道選手権大会」で、見事優勝を果たした新田暁高校の岸田 風穂さんが、先日、優勝の報告に来てくださった。
現在、高校1年生である岸田さんは、小学校1年生から空手道を始め、今回、出場した国際親善空手道大会で5連覇を成し遂げられた。
今後も岸田さんの更なるご活躍を、とても楽しみにしている。
次、順不同にはなるが、8月2日に、太宰府市にある九州国立博物館を会場に開催される「全国高等学校歴史学フォーラム2025」において、高崎北高等学校JRC部歴史研究班の生徒が、研究発表を行う。
研究テーマが「庚申信仰の現状と、地域社会における現代的意義について」である。
理科系の分野については、例えば数学オリンピックなど、数々のこうした機会があるが、文科系になると全国規模の発表というのは、非常に数が少ない状況にある。
そうした中で、全国から応募のあった研究成果の審査を通過した10校のうちの1校として高崎北高等学校が発表する。
生徒達が自ら関心のある分野を掘り下げて、全国の大舞台で発表を行う機会というのは本当に素晴らしいことで、嬉しく思っている。
次に、第27回日本水大賞2025、日本ストックホルム青少年水大賞について報告する。
7月8日に日本科学未来館において、第27回日本水大賞2025日本ストックホルム青少年水大賞の表彰式が行われた。
吾妻中央高等学校環境工学研究部が大賞グランプリを受賞して、秋篠宮皇嗣殿下ご臨席の表彰式において、皇嗣殿下から直接表彰状を授与された。
これもグランプリというのは本当に素晴らしい賞である。
彼らのテーマは地域の農業を守りたい、老朽化した農業用水路の保全に向けた高校生の取り組みと題した、ドローンを使った活動である。
水路の壊れているところを、地域の皆様がそれを全部確認していくのは非常に大変なことだった。それを高校生がドローンを使って確認するといった活動である。これが実践的で地域への社会貢献が大きい取り組みであるとして、高く評価されている。
次に、県立高校3校によるtsukurunサテライトの開校について、報告をさせていただく。
県立高校においても、昨年3月にtsukurunサテライト3校、高崎女子、伊勢崎、吾妻中央に開設し、地域の小中学生向けに、新たな価値を創造するデジタルクリエイティブ人材の育成を目標とする群馬県の事業の1つとして、開放した。
今年度について、いよいよ3校における地域の小中学校への開放が、7月から始まる。先月、市町村教育委員会を通して、県内市小中学校に周知を行った。
県教育委員会としては、地域の子ども達、また、設置校の生徒達の多くがtsukurunサテライトを利用し、またTUMOを利用し、デジタルクリエイティブ活動に興味を持ってくれること、また同士との出会いなどを通して、より一層種成長してくれることを期待している。
次に、「トビタテ!留学JAPAN新・日本代表プログラム」に群馬県が採択されましたので報告させていただく。
こちらは文部科学省及び日本学生支援機構が実施している官民協働の海外留学支援制度である「トビタテ!留学JAPAN新・日本代表プログラム」において、本県の群馬グローバル人材育成事業が、全国で3県のみであるが、富山県、京都府とともに採択をされた。
本事業は、生徒が自ら設定した地域探求に関する課題解決について、留学を通して見聞を深め、群馬県にイノベーションを起こすことのできるグローバル人材の育成を目指すものである。
本事業により、語学力、また、家庭の経済状況等にかかわらず、生徒たちが探求したい、挑戦したいという思いを、実現できるようにしていく。
今まで採択されたのは、石川、静岡、滋賀、福島、高知の5県のみだった。
大変難しいプログラムに、本県が採択され、こうしたチャンスを得ることが出来たことは、本当に素晴らしいことである。
本事業により、本県の高校生が探求に伴う留学に積極的にチャレンジできるよう準備を進めていく。
続いて、主な出席行事について報告したい。
6月27日に、知事と教育委員との協議の場である「総合教育会議」が開催され、委員の皆様にご出席いただいた。
会議では、「群馬モデルの部活動の在り方、部活動の地域展開」をテーマに知事との意見交換を行った。
また、河添委員とともに7月15日、16日の2日間、青森市で行われた「全国都道府県教育委員会連合会」の総会に、出席した。
会議では、私は「公立高等学校の魅力向上と教育現場におけるデジタル技術の活用」をテーマに、各県の教育長さん方と意見交換を行ってきた。
どの県でも、地方の小規模校や専門高校の魅力向上に向けて努力されており、デジタル技術を活用した遠隔教育や校務における生成AIの活用など、様々な取組を行っていることが分かり、それらを参考に群馬県も進めていきたいと考えた。
今後も他県と情報交換を図りながら、本県の取組を進めていきたいと思っている。
私からは以上である。
それでは、各教育委員から意見や報告をお願いする。
(河添委員)
6月21日の総合教育会議に参加をさせていただいた。
教育は人なり、教師がより良いコンディションで子ども達と関わるために、また少子化への対応のために、最重要課題の1つである「部活動の地域展開」について、働き方改革、教員不足解消と合わせて、より迅速に推進していく必要がある。そのために、知事が参加してくださったので、知事の発信力とリーダーシップにより、さらに、教育委員会と知事部局の加速化に向けた体制整備と関係機関や地域、保護者の理解促進を進めていけるように願い、子どもと教員、両方の環境整備や、ぐんまモデルを発信していただけたらと思い、お話をさせていただいた。大変勉強になった。
続いて7月4日に、学校訪問で川場学園と沼田高校へお世話になった。
2校とも教育環境整備に何年もかけて、今年開校した学校である。特に川場学園では、教育長をはじめ、地域や保護者、関係機関、保護者や児童生徒の思いが詰まっていることがよく分かった。
沼田高校については、前に継嗣式に出席させていただいているので、今日は川場学園のことを、お話をさせていただく。
自分も小学校に勤めていた経験があったので、川場学園の、何よりも子ども達を大切にし、愛情を込めて主体や基礎基本を含む方針、特に、豊かな心に支えられた、確かな学力、そして、認知能力と非認知能力をバランスよく育み、さらに特色を生かして、体験活動や異年齢交流、地域の皆さんを大切に関わり合いながら、自信につなげていく方針は、本当に素晴らしくて、まさに理想の群馬モデルに非常に近い形なのではないかと感じた。
最後に、7月15日、16日に教育長と、青森県で開催された全国都道府県連合会の総会、そして協議会に参加をさせていただいた。
内容は、非常に密度の濃いもので、公立高校教員の不足解消等と、それに向けた文部科学省担当者からのご説明も、本当に勉強になった。
これから教育委員の皆様と事務局の皆様にも共有し、課題解決の加速化を進めていけるようにしたいと考えている。
特に働き方改革の部分で言うと、文部科学省の担当官からの「教師を取り巻く環境整備について」お話をいただいたので、紹介をさせていただきたい。
まず状況について、大分、改善されてきたとはいえ、教師としてやるべきこと、学校職員として分掌でやるべきこと等、既に業務量が溢れている。
翌日以降の教材研究や、その日の子ども達の状況の振り返り、丸付けを含めた評価は、持ち帰りや土日に行うなどのことがまだある、そのような状況である。
さらに、教師でなくても出来ることが提示されたが、どなたにそれを受け持っていただくかとなると、人、そして、お金が、思うようにいかない。
ボランティアの皆さんや保護者に依頼することも、地域状況によってはとてもよく進んでいく場合と、難しくて、継続性も危ぶまれる場合もある。
そのような中、国は教師の職務の特殊性と高度な専門性をしっかりと位置付けているのがよく分かる。
「業務が多すぎる」、「減らして、健康に働く環境を整えて欲しい」という現場の声を、データとともに示してくださり、学びの専門職として、働きやすさと働きがいの両方を、総合的に推進していこうとしている方針が、しっかりと示された。
1つ目は働き方改革のさらなる加速化、2つ目が指導運営体制の充実、3つ目が、教師の処遇改善である。
特に、たくさんある中で、自分がピックアップしたのは、教師が担う業務、教師以外の参画を促す業務等3分類が、以前に示されたが、それをアップデートし、整理し直していくということ、例えば、学校プールの管理等といったことが整理されて、出されてくるということだった。
多様化、複雑化、困難化している学校現場で奮闘する先生方が毎日疲弊していたら、翌日も多感な、多様な、個性を持つ大切な子ども達に向け、個別最適で協働的な主体的な学び、適切な生徒指導を行うことが難しくなる。
教師の感情労働にはその特殊性にも関わり、本当に膨大な量であるので、コンディション不良が及ぼす影響が子ども達に現れてしまうのは、本当に大変なことである。
もちろん、先生方の健康が、危ぶまれることはそれ自体がいけないことである。
より良い伴走、指導支援を行う、子供たちの成長に欠かせない教員が、より良いコンディションで子ども達と向き合えるよう、環境整備は、いま一番大切な教育改革の1つであるということを、文部科学省の担当官からの話からも、改めて感じることが出来た。
また、お話の中で特に力強く感じたのは、今までビルド&ビルドと、ビルドをたくさんしてきた教育政策をビルドするのであれば、その分、スクラップが必須であるという、そういった考え方を、国も示しているということである。
令和8年4月に施行予定の法律で、教育委員会における実施確保のための施策が示され、教育委員会に対して文部科学大臣が定める指針に則して、教員の業務量の適切な管理と健康福祉を確保するための措置として、「業務量管理・健康確保処置の実施計画」と呼ばれる計画の策定、公表、それから総合教育会議への報告を義務づけることが示された。
県から市町村教委への指導助言も努力義務となることが示され、学校にも実施していくことが示された。
県としては、策定する例として、各県において、その取り組みの施策と具体と点検評価も含めて、その働き方改革に特化した推進室のような部署を設けているというところが増えてきてると感じている。
例えば、学びのイノベーション推進室が学びのぐんまモデルを策定していくのと同様に、今後、国の求める働き方改革や魅力向上を専門に取り組んでいく体制を強化するために、例えば、働き方改革の推進室のような部署を作り、働き方や魅力向上の群馬モデルを策定、公表し、評価し、総合教育会議に報告していく、そのような流れになっていくと感じている。
色々な情報交換の中で、群馬県と同様に、他の都道府県も本気で、より具体の日程を整えてきていると感じた。
発信についても、群馬県もたくさんの発信をしているが、他の都道府県も発信をしていると感じている。
地道な、そして大胆な取り組みも含めて、保護者、それから地域関係機関、全県で取り組もうとしている勢いを、全体的に感じ取ってきたので、群馬県もさらに推進出来る、或いはリードしていけると感じている。
最後に、国の措置の中の1つの例で、1人当たりの担当授業時数の削減が項目で示されていた。
資料をいただき、お話を聞き、他の都道府県の教育委員や教育長様と交流をさせていただきながら、改めて子ども達に活かされていく教育の環境整備や教員を取り巻く環境整備が加速化していくと良いと感じ取ってきたので報告をさせていただいた。
(日置委員)
6月27日に総合教育会議に参加し、群馬モデルの部活動のあり方として、地域展開について意見交換を行った。
話を聞く中で、群馬県でも部活動の地域展開が着実に進んでいると感じた。
新町スポーツクラブは設立されてから20年以上が経過しているが、小出理事長の話では、部活動の地域展開は、少子化によって従来の部活動が維持できなくなっていることや、教員の負担軽減のための受け皿の確保といった学校や地域の課題として捉えるのではなく、「生涯にわたってスポーツを楽しむ」「スポーツツーリズムの推進」といった視点を取り入れた地域活性化の一環として考えることが重要であるという話が非常に印象的だった。
前橋市の取り組みでは、週末の部活動を廃止し、「多様な学びの日」を提供していることが紹介された。
中学生の保護者などが立ち上げた30以上の団体があり、生徒は部活動とは異なるスポーツや文化活動を選択できるというもので、非常に素晴らしい取り組みだと感じた。
地域展開を進める上で、地域ごとに課題は異なるが、小出理事長の話にもあったように、観光振興、生涯学習、高齢者の健康維持など、地域活性化の観点から多様な要素を取り入れ、まずはその地域の課題や強みを認識し、住民が積極的に関与したくなるような仕組みづくりを進めていく必要があると感じた。
7月4日には、学校訪問で川場学園を訪れた。
川場小学校・川場中学校は非常に伝統ある学校であり、構想から10年をかけて、義務教育学校の利点を最大限に生かすよう綿密に計画された学校であると伺った。
9年間の教育課程を3つのブロックに分け、各ブロックの最高学年でリーダーシップを3回発揮できるよう工夫されている。
掃除やレクリエーションなどでは、各ブロックのリーダーが企画を担い、異学年交流を意図的に設計している様子が見られた。
非認知能力の育成に関しては、子どもたちが「自分の能力や心をどう伸ばしたいか」を常に意識できるよう、専用のワークシートが作成されているとのことだった。
最も驚いたのは、地域ぐるみの支援体制である。
「うちの子もよその子も川場の子。川場の子は川場の宝。だからみんなで育てましょう」という言葉が、まさに実践されていると感じた。
村の人口は約3,000人だが、延べ3,046人のボランティアが活躍しているという話だった。
算数の授業やプールの見守りなどに、地元の方々が積極的に関わっている様子を見学した。
不登校の子どもが極端に少ないことについて教頭先生に質問したところ、地元の方々が子どもたちをしっかり支えており、「明日も学校に行きたい」と思えるような環境が整っているのではないかという話だった。
また、宮内教育長は「川場学園の先生方には転勤があるが、たくさんのボランティアが学校に関わっていることで、川場の良い伝統が守られている」と話しており、非常に印象的だった。
教員の働き方が大きな課題となっている中で、川場村のように地域ぐるみで子どもを育てるという考え方が他の地域にも浸透すれば、働き方改革にも大きく貢献するのではないかと感じた。
統合して開校した新沼田高校については、写真で見た近代的な校舎を楽しみにしていたが、実際に訪れてみると、非常に開放感があり、生徒たちは様々な場所で自由に学び、協働的な学習が行われている様子が見られた。
伝統ある両校が統合したことから、お互いの特色を新沼田高校にどう活かすか、どのような学校にしていくかについて、生徒同士が統合前から検討を重ねてきた経緯を懇談の中で紹介してもらった。
交流イベントの企画、制服や校則の検討、文化祭の準備などに、生徒たちが深く関わっており、「生徒が提案し、生徒が作り上げた」という自負が感じられた。
「後輩に伝えたいことは何か」と質問したところ、「生徒が主体となって物事を進めてほしい」という答えが真っ先に返ってきた。
「自分で考え、自分で決めて、自分で動く」という群馬県の教育ビジョンを実践したことが成功体験となっており、それを後輩に伝えたいという強い気持ちが表れていたように感じた。
(小島委員)
6月27日の総合教育会議に出席した。
自分が特に関心を持っているのは、学校からクラブ活動を地域へ移行するという話ではなく、受け入れる側である「地域」の在り方である。
その「地域」とは、どの範囲を指すのか。行政区域全体では広すぎるように感じるし、中学校単位では狭すぎる懸念がある。
現時点では、その地域の体制整備が十分にできていないため、学校側がクラブ活動を移行しようとしても、実際には難しいのが現状だと感じている。
しかしながら、「地域をつくる」ということ自体は、今後の豊かで安全な暮らしを支える観点からも、不可欠な取り組みである。
会議でも述べたが、災害時に企業はBCP(事業継続計画)を策定し、地震などの発生後すぐに活動を再開できるよう、飲料水や非常食を備蓄して災害発生に備えている。
一方で、災害が起きた際に最初に立ち上がるのは、地域の助け合いである。
そうした両者が助け合う意味でも、地域の体制整備はできるだけ早い段階で進める必要がある。
その中に、クラブ活動のような取り組みが含まれ、スポーツを通じて豊かな生活が送れるようになれば、地域内での相互作用が生まれ、非常に良い効果が期待できる。
企業としても、何か貢献できることがあるのではないかと考えている。
学校訪問については、川場村を視察したのだが、川場村に対して、以前から「ミニ神戸市」のような印象を持っている。
神戸市は「神戸株式会社」とも言われるほどで、山を切り崩して埋め立てをし、跡地をニュータウンにするなど活気なアイデアで仕事を進めるし、運営も非常に上手である。
川場村も同様に、村全体で教育部門を他の産業と同じように力を入れて取り組んでいる姿勢が見られ、川場らしさを感じることができた。非常に良い印象を受けた。
沼田高校については、大学のキャンパスのような自由な雰囲気があると感じた。
生徒たちには、生徒同士で協議した内容を、それぞれの高校やクラスに持ち帰ってどのように検討したのかを質問したところ、協議内容を充分に伝え、議論したという非常に感心する回答が返ってきた。
(中澤委員)
6月27日の総合教育会議に参加した。
テーマは「部活動の地域展開」であったが、当初は学校内の部活動の機能を地域に展開・移行していくという視点で考えていた。
しかし、小島委員の発言にもあったように、部活動の移行は単なる機能の移転ではなく、「その地域で暮らしていく」ということと切り離して考えるべきではなく、根本的な地域づくりの一環であることが分かった。
新町スポーツクラブの例を見ても、その地域で育った子どもたちが指導者となり、高齢者も参加するような形で、地域全体がスポーツクラブとして機能している。
このような事例からも、地域をつくっていくという視点が極めて重要であると強く感じた。
学校訪問では、川場学園と沼田高校を訪問した。
川場学園については、小島委員の話にもあったように、豊かな学校であり、豊かな地域であるという印象を強く受けた。
自然環境や地域性が豊かであり、インフラも整っていて、人の流れもある。構想10年にわたる教育を考えてきた人材、教育長をはじめとする熱意ある人々が存在し、その場所を大切に思う地域の人々がいる。
学校を大切に思うからこそ、地域の人々が学校に関わる流れが自然に生まれているのだと感じた。
また、非認知能力の育成にも取り組んでいるが、それは学校がもともと持っている土壌に根ざしているのではないかと感じた。
子ども自身が目標を設定し、それに向かって取り組む姿勢があり、意見を述べる機会も多い。
授業では、自分の考えを文章にしたり、表現したりする機会が自然に多く設けられている。
日置委員の話にもあったように、リーダーになる機会も多く、自分が次を見て考えて動く、自分がどうすれば良いかを考えて行動するという姿勢が育まれている。
こうした取り組みが、非認知能力の育成と密接に関係していると感じた。
沼田高校では、統合という大きな出来事を乗り越え、生徒たちが学校生活に前向きに取り組んでいる様子を見ることができた。
生徒会の皆からは、合意形成のプロセスを自分たちで段取りを組みながら進めてきたという話を聞いた。
制服や校則、イベントなどについても、「自分たちだけで決めても意味がない」「みんなが納得し、ついてきてくれるにはどうすれば良いか」といった視点で取り組んでいた。
自分が納得すれば良いという考え方ではなく、他者を巻き込みながら合意を形成し、物事をつくり上げていくという姿勢が見られ、高校生の時期にそのような経験を積んだことが、生徒たちの自信につながっているように感じた。非常に頼もしく思った。
(平田教育長)
それでは、関係所属長から報告をお願いする。
ご質問はすべての報告が終了した後、一括して行う。
(1)令和7年度群馬県公立高等学校入学者選抜日程及びWeb出願システムに関するアンケート調査結果について
高校教育課長、資料1 (PDF:535KB)により報告。
(2)県立中央中等教育学校入学者選抜に係る出願方法の変更について
高校教育課長、資料2 (PDF:347KB)により報告。
(3)2025年度官民協働海外留学支援制度トビタテ!留学JAPAN新・日本代表プログラム「拠点形成支援事業」への採択決定について
高校教育課長、資料3 (PDF:343KB)により報告。
(4) SAH IGNITE(イグナイト)3.0の開催について
高校教育課長、資料4 (PDF:111KB)により報告。
(5)令和7年度インクルーシブ教育推進に係る有識者会議について
特別支援教育課長、資料5 (PDF:175KB)により報告。
(6)ぐんまインクルーシブフェスタ2025 ~みんなで知ろう みんなで創ろう~ について
特別支援教育課長、資料6 (PDF:1.4MB)により報告。
(7)ぐんま昆虫の森開園20周年記念講演会の開催について
生涯学習課長、資料7 (PDF:167KB)により報告。
(平田教育長)
ただいまの報告について、委員から意見や質問があるか。
(河添委員)
令和7年度の公立高等学校の入学者選抜日程とWeb出願システムに関するアンケート調査結果を拝見した。
こうした振り返りをもって次に進んでいけることは、非常にありがたいと感じている。
インタビューシートについては、中学校の先生方が丁寧に支援していたこともあり、入学者や保護者からは「特に問題はなかった」という回答が多かったように思う。
しかし、回答者はおそらく中学校の担当教員であると推察されるが、実際には問題があった学校も少なくなかったのではないかと感じている。
業務負担についても、「どちらかといえば軽減された」という回答がある一方で、「どちらかといえば負担が増えた」とする回答が中学校の約31%に見られた。
これは導入初期特有の課題なのか、それとも構造的な問題として解決が必要な状況なのか、もし分かれば教えてほしい。
(高校教育課長)
今回のアンケート結果を通して、中学校の担任の先生を中心に、非常に丁寧で行き届いた指導が行われていたことが分かった。
ヘルプデスクなども開設されたが、インタビューシートやWeb出願の登録については、子どもたちはまず信頼している先生に相談することが多く、やはり中学校の担任の先生が最初の窓口となっている。
また、インタビューシートをPDFでWeb出願システムにアップロードする必要があるため、パソコン操作に慣れていない生徒や、通信環境が整っていない家庭もあり、そうしたやり取りに時間がかかってしまったケースも多かったのではないかと推測している。
導入初期特有の負担はある程度避けられないが、今後は継続的に負担軽減を図っていく方針である。
まだ検討段階ではあるが、例えば「3の(1)」に記載したFAQの導入については、保護者が不明点を学校の先生に尋ねる代わりに、システム上で質問を入力すると予測変換により「このことですか?」と表示され、AIが回答するような仕組みを検討している。
このように、少しずつではあるが、先生方に過度な負担がかからないよう配慮していきたいと考えている。
また、中学校や市町村教育委員会にはその都度話を聞き、実態を把握しながら改善を進めていく予定である。
(平田教育長)
「トビタテ!留学JAPAN新・日本代表プログラム」については、この計画を作った高校教育課が頑張ったことと、小中段階もであると思うが、県内の県立高校の探求授業が、相当レベルが高いことがあるかと思う。
先ほどお話した「水大賞」や「歴史大賞」もある意味、探求の質の高さを表していると思う。
もう1つ、非常に大事なのは企業の皆様方のご協力である。これは、高校生の留学に関しての費用の一部をご寄附いただくという仕組みになっており、本当にたくさんの企業様からお申し出をいただいて、それがあったからこそ、ここに応募することができた。心から感謝をしている。
また、「インクルーシブフェスタ」については、昨年までは県庁内で行っていたが、参加された方々などのご意見から、県庁に来られるような、もともと興味をお持ちの方々だけではなく、例えばイオンモール高崎等だと、たまたま行ったときに「何かやってる」ということで来てくださる方々もいる。
是非、そういう方々に対してのイベントを開催してはという、ご提案があり、特別支援教育課が実現させたものである。
ぜひ多くの方々に来ていただくことを心から願っている。
(河添委員)
昨年のインクルーシブフェスタも素晴らしかったと思うが、地域に開いて、一歩前進し、広がっていくイメージで、素晴らしいと思う。
また、「トビタテ!留学JAPAN新・日本代表プログラム」も本当に素晴らしいことであると思う。費用や語学力に縛らず、探求をしていくんだ、海外に行ってこういうことをやっていくんだということが、生徒に開かれていくということは、本当に価値あることだと思う。ご尽力に感謝する。
(中澤委員)
「トビタテ!留学JAPAN新・日本代表プログラム」について、今までは実業系高校からの留学に限られていたと思う。何となく語学優先のようなところがあったと思うが、群馬県の中で実業系の高校の充実が目立つと日頃から感じている。食や農業、園芸そしてスポーツ、歴史芸術、建築、IT、いろんな角度の可能性があるが、今まで留学となかなか結びつかない感じがあった。何となく既存の概念で留学を見ている気がするので、ぜひいろいろな高校に周知をしていただき、できるだけ、留学の可能性を十分に考えていただけるような、アプローチを意識的にしていただけるとありがたい。ぜひお願いしたい。
それから、「インクルーシブフェスタ」も、地域に開かれた形で開催されるということを、とても嬉しく思う。
様々な高校生が、トークセッションを一堂に会して行うというイベントは、とても興味深い。
参加する生徒は、高校や特別支援学校からの希望があって、参加することになったのか。
(特別支援教育課長)
最初に高校・特別支援学校に対して出場を募るとともに、こちらからも声掛けを行った。その中から、自分から出たいという生徒もいて、それぞれの学校の先生と話し合って決定した。基本的には興味があって参加してくれている。先日、参加する高校の先生から、これに参加するために生徒がすごく工夫していると聞いた。フェスタに向けて素晴らしい準備をされて、夏休みの思い出になっているとのことでもあり、我々も期待している。
(中澤委員)
工夫するということは、きっといつも発想しないところまで考えたりしていると思うので、とても楽しみなことだと思う。
(平田教育長)
SAH IGNITE(イグナイト)3.0についても、昨年OCEのグローバルフォーラムを開催したときに、例えば、「その意見、いい意見ね」とか、何か言い淀んでいると「それはそういうこと」と言ってしまう、それは対等ではない。そうではなく、生徒と先生が対等な立場で行うということは、先生も我慢して、生徒を待つということが、生徒と大人が本当に対等な立場になるのだということを学んだ。
そのことを早速このSAH IGNITEという形で行う。渋川女子高等学校が進んでやってくれている。
(高校教育課長)
基本的には、SAHの指定校協力校の生徒、先生、特に生徒に自分達で何をやるかというところから、決めてもらっている。
今回は、パネルディスカッションで、今年度から指定校に加わっていただいた渋川女子高校の生徒が、昨年度から非常に活発な活動をしており、是非にやりたいと言っていただき、生徒と先生がフラットな立場で話し合いを行うので、ぜひお時間あればご覧いただきたい。
(平田教育長)
昆虫の森の職員もロゴを作ったり頑張っているので、お時間のある方はお越しいただきたい。
(河添委員)
昆虫の森の開園の20周年記念で非常におめでたいことであると思う。
8月3日の記念講演会を皮切りに、もし他に何かイベントなどがあれば教えていただきたい。
(生涯学習課長)
前後するが、20周年ということで8月1日に、現地でくす玉を用意し開園記念セレモニーを行った。
また、20周年限定の缶バッチを用意したり、7月から「20年の歩み」と題して、これまで開催してきた企画展を振り返るという企画展をやっている。
それから、先日ご報告させていただいたが、「未来プロジェクト」と題して、昆虫の森を今後どう進めていくかということについて、先日、外部委員の皆さんにご参加いただき、協議を始めたところである。
(河添委員)
本当に昆虫の森も、天文台も、少年科学館も、みんな子ども達にとって大切で、とっても楽しい有意義な施設だと思うので、ぜひ今後も発信していただきたい。
(平田教育長)
それでは、以上で教育長事務報告を終了する。
11 議案審議(非公開)
ここで、平田教育長から、これからの審議は非公開で行う旨の発言があり、傍聴人及び取材者は退室した。
第24号議案 臨時代理の承認について(群馬県産業教育審議会委員の任命について)
高校教育課長、第24号議案原案について説明
異議なく、原案のとおり承認
第25号議案 教職員の人事について
学校人事課長、第25号議案原案について説明
異議なく、原案のとおり決定
第26号議案 教職員の人事について
学校人事課長、第26号議案原案について説明
異議なく、原案のとおり決定
第27号議案 教職員の人事について
学校人事課長、第27号議案原案について説明
異議なく、原案のとおり決定
第28号議案 教職員の人事について
学校人事課長、第28号議案原案について説明
異議なく、原案のとおり決定
12 教育委員会記者会見資料について
教育委員会記者会見資料について、総務課長が説明。
13 閉会
午後2時30分、平田教育長、教育委員会会議の閉会を宣す。