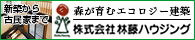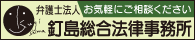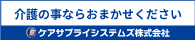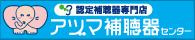本文
令和7年度答申第2号
第1 審査会の結論
処分庁による令和5年5月1日付け、同月9日付け及び同月12日付け審査請求人に対する一時扶助決定(以下それぞれ「本件処分1」、「本件処分2」及び「本件処分3」という。)に係る審査請求には一部理由があるため、本件処分1のうち温水便座に係る部分を行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第46条第1項の規定により取り消すとともに、本件審査請求のうち電子レンジに係る部分を法第45条第2項の規定により棄却し、カーテンに係る部分を同条第1項の規定により却下すべきである。
第2 審査関係人の主張の要旨
1 審査請求人
(1) 障害や病気により、○○、○○が著しく○○が困難である。温水便座について、○○課に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)における「日常生活用具給付等事業」による給付を相談したが、自身の障害の程度では基準に該当しなかった。温水便座は2015年に普及率が70%を超え、生活必需品と言える。したがって、生活保護法(昭和25年法律第144号)上の家具什器費の特別基準の適用を申請した。処分庁は手持ち金により購入可能との反論をしているが、購入は極めて困難であった。コンロがなく、調理ができず節約にも限界があった。
(2) 障害者加算は単なる優遇措置ではなく、差別環境を是正するためのものである。処分庁は生活保護受給世帯での温水便座普及率を理由に、最低生活に必要ないと判断しているが、自身は障害者であり、健常者世帯と比較する意味がない。
(3) 転居に際し、インターネット検索で温水便座付物件は見つからなかった。サイトに載っている物件はおとり物件が多い。
(4) 電子レンジは故障しており、湯も沸かせない状態であったため、新たに購入し、領収書をもって申請した。暖房器具がなく、湯たんぽで越冬する以外の方法がなかったが、電子レンジが更に故障したため、買い換えた。
(5) 家具什器費は必要性・緊急性があるものと処分庁は認識しながら、保護開始から決定通知発行まで3か月以上要している。令和5年○月○日に申請書(生活保護申請、家具什器費、被服費)を持参したが、受理されなかった。遅すぎであり、生命の危険を感じた。
(6) カーテンに関する処分を取り消す裁決を求める。また、処分庁は生活費の中でやり繰りして買うよう助言したが、そのことに対して納得していない。
2 審査庁
審理員意見書のとおり、本件処分1のうち温水便座に係る部分を取り消すとともに、本件審査請求のうち電子レンジに係る部分を棄却し、カーテンに係る部分は却下すべきである。
第3 審理員意見書の要旨
1 家具什器費の基準額について
審査請求人の主張する特別基準の適用が、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年4月1日厚生省社会局長通知。以下「局長通知」という。)第7―2(6)における32,300円の基準額を指しているのか、51,500円の基準額を指しているかは不明であるが、「生活保護問答集について」(平成21年3月31日厚生労働省社会援護局保護課長事務連絡。以下「問答集」という。)問7-43(答)によると、真にやむを得ない事情による必要があり、災害にあい家具の大部分を失った場合や、退院して新たに自活する際に全く家具什器を所持していない場合等であれば、51,500円の範囲内で特別基準の設定ができることが定められている。
処分庁はケース記録の中で、審査請求人に災害等の特別な事情があったわけではなく、審査請求人の場合は通常の転居によるものであること、家具が一部用意できており、転居費用は○○から支給されていること等を確認している。これらの事情を勘案すると、審査請求人の家具什器の申請は真にやむを得ない事情とは言えず、51,500円の範囲内での特別基準は設定できないとした処分庁の判断に誤りは認められない。
2 本件各申請の認定基準該当性について
(1) 温水便座に係る部分
審査請求人の身体障害診断書では、○○については半介助が必要とされており、また、審査請求人が単身世帯であることを踏まえて、審査請求人が温水便座がない状況で生活が送れるかについて処分庁が作成したケース記録の中では検討が十分になされていない。
したがって、処分庁が温水便座の家具什器費を支給しない根拠としている、普及率の観点及び審査請求人の障害の状況のいずれについても検討が不十分であると言わざるを得ない。
(2) 電子レンジに係る部分
審査請求人は○○での保護廃止の翌日から○○で保護開始されており、生活保護の空白期間は生じていないため、局長通知第7-2(6)ア(ア)が想定する「保護開始時」に当てはまらないと言える。したがって、不支給とした処分庁の判断に誤りはない。
(3) カーテンに係る部分
審査請求人が処分庁に対してカーテン代金を申請した事実が存在しないため、審査請求人が求める処分の取消しの原因となる処分が存在しない。したがって、審査請求人の主張は認められない。
3 結論
以上のとおり、本件審査請求には一部理由があり、法第45条第1項及び第2項並びに第46条第1項の規定により、本件処分1のうち温水便座に係る部分は取り消されるべきであり、本件審査請求のうち電子レンジに係る部分は棄却されるべきであり、カーテンに係る部分は却下されるべきである。
第4 調査審議の経過
当審査会は、本件諮問事件について、次のとおり、調査審議を行った。
令和7年5月15日 審査庁から諮問書及び諮問説明書を収受
令和7年5月23日 調査・審議
令和7年6月27日 調査・審議
第5 審査会の判断の理由
1 審理手続の適正について
本件審査請求について、審理員による適正な審理手続が行われたものと認められる。
2 本件処分1、本件処分2及び本件処分3に係る法令等の規定について
(1) 臨時的最低生活費(一時扶助費)は、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日厚生省事務次官通知。以下「次官通知」という。)第7において、次のとおり示されている。
最低生活費は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別等による一般的な需要に基づくほか、健康状態等によるその個人又は世帯の特別の需要の相異並びにこれらの需要の継続性又は臨時性を考慮して認定すること。
(中略)
2 臨時的最低生活費(一時扶助費)
臨時的最低生活費(一時扶助費)は,次に掲げる特別の需要のある者について、最低生活に必要不可欠な物資を欠いていると認められる場合であって、それらの物資を支給しなければならない緊急やむを得ない場合に限り、別に定めるところにより、臨時的に認定するものであること。
なお、被服費等の日常の諸経費は、本来経常的最低生活費の範囲内で、被保護者が計画的に、順次更新していくべきものであるから、一時扶助の認定にあたっては、十分留意すること。
(1) 出生、入学、入退院等による臨時的な特別需要
(2) 日常生活の用を弁ずることのできない長期療養者について臨時的に生じた特別需要
(3) 新たに保護開始する際等に最低生活の基盤となる物資を欠いている場合の特別需要
(2) 局長通知第7―2(6)アでは、家具什器費に関して、次のとおり示されている。
被保護世帯が次の(ア)から(オ)までのいずれかの場合に該当し、次官通知第7に定めるところによって判断した結果、炊事用具、食器等の家具什器を必要とする状態にあると認められるときは、32,300円の範囲内において特別基準の設定があったものとして家具什器(イ及びウを除く。)を支給して差し支えないこと。
なお、真にやむを得ない事情により、この額により難いと認められるときは、51,500円の範囲内において、特別基準の設定があったものとして家具什器(イ及びウを除く。)を支給して差し支えないこと。
(ア)保護開始時において、最低生活に直接必要な家具什器の持合せがないとき。
(イ)単身の被保護世帯であり、当該単身者が長期入院・入所後に退院・退所し、新たに単身で居住を始める場合において、最低生活に直接必要な家具什器の持合せがないとき。
(ウ)災害にあい、災害救助法第4条の救助が行われない場合において、当該地方公共団体等の救護をもってしては、災害により失った最低生活に直接必要な家具什器をまかなうことができないとき。
(エ)転居の場合であって、新旧住居の設備の相異により、現に所有している最低生活に直接必要な家具什器を使用することができず、最低生活に直接必要な家具什器を補填しなければならない事情が認められるとき。
(オ)犯罪等により被害を受け、又は同一世帯に属する者から暴力を受け、生命及び身体の安全の確保を図るために新たに借家等に転居する場合において、最低生活に直接必要な家具什器の持合せがないとき。
(3) 問答集問7-43では、家具什器費における実施機関限りの特別基準設定について、次のとおり示されている。
問7-43 家具什器費における実施機関限りの特別基準設定について
(問) 局第7の2の(6)のアのなお書にいう「真にやむを得ない事情」とは、どのような事情が考えられるか。
(答) 例えば、災害にあい家具の大部分を失った場合や、長期間入院していた単身者が、退院して新たに自活するに際し全く家具什器を所持していない場合などが考えられる。家具什器費の認定に当たっては地域における低所得世帯の生活実態、当該世帯人員の状況等からみて、最低生活に必要な最小限度の家具什器の程度を的確にとらえるとともに、例えば、罹災世帯であれば消失の程度、他からの援助の有無等を十分調査検討の上取り扱う必要がある。
(4) 局長通知第3では、家具什器費に関して、次のとおり示されている。
資産保有の限度及び資産活用の具体的取扱いは,次に掲げるところによること。(中略)
4 生活用品
(4) その他の物品
ア 処分価値の小さいものは,保有を認めること。
イ ア以外の物品については,当該世帯の人員,構成等から判断して利用の必要があり,かつ,その保有を認めても当該地域の一般世帯との均衡を失することにならないと認められるものは,保有を認めること。
(5) 内閣府経済社会総合研究所景気統計部が実施した「消費動向調査(令和6年3月実施調査結果)」では令和5年3月末時点の温水洗浄便座の全国普及率は81.7%であり、総務省が実施した「平成26年全国消費実態調査」では平成26年の本県での温水便座の普及率が71.4%であった。
3 本件処分1、本件処分2及び本件処分3の妥当性について
(1) 温水便座に係る部分
審査請求人は○○の障害があり、診断書によれば○○には半介助が必要であるとされ、温水便座の家具什器の申請時にも、そのことを申請書に記載している。また、審査請求人の障害の程度では、重度障害者等の日常生活を円滑にするための用具を給付し又は貸与し、福祉の増進に資することを目的とした日常生活用具給付等事業の特殊便器の支給対象にならなかった。
問答集問7-43(答)では、地域における低所得世帯の生活実態、世帯人員の状況等を鑑みて、最低生活に必要な最小限度の家具什器の程度を捉える必要がある旨の記載がある。
また、次官通知第7では、最低生活費について、所在地域別等による一般的な需要を考慮することとされているほか、局長通知第3-4(4)イでは、資産保有の限度について、世帯の人員、構成等から必要性を判断し、保有を認めても当該地域の一般世帯との均衡があれば、保有を認めることとされている。
処分庁は弁明書において、温水便座の普及率の観点と日常生活用具給付等事業に該当しないこと等を理由として、温水便座に関する家具什器費の支給を行わない決定をしている。
温水便座について、処分庁は全世帯での普及率が平成27年に70%を超えている中で、障害者世帯での普及率が60~70%であり、障害者世帯での普及率が著しく高いわけではないことを言及している。加えて、生活保護受給世帯での普及率が14.9%と低いことをもって、最低限度の生活に必要と認めなかった。
資産活用の観点では、局長通知第3-4(4)イで示されているとおり、当該地域での普及率が70%程度あれば保有を認めることが示されている。○○の世帯における普及率は不明だが、平成26年の群馬県における普及率は71.4%であり、令和5年の全国での普及率は81.7%である。一般的に都市部の普及率は県全体よりも高いと考えられる。
また、処分庁は障害福祉の観点から審査請求人の最低生活に温水便座が必要ではないと判断している。
しかしながら、審査請求人の身体障害診断書では、○○については半介助が必要とされており、また、審査請求人が単身世帯であることを踏まえて、審査請求人が、温水便座がない状況で生活が送れるかどうかについて、処分庁が作成したケース記録の中では検討が十分になされていない。
したがって、処分庁が温水便座の家具什器費を支給しない根拠としている、普及率の観点及び審査請求人の障害の状況のいずれについても検討が不十分であると言わざるを得ない。
(2) 電子レンジに係る部分
処分庁は電子レンジに関して、家具什器費の申請却下理由をケース記録において、「○○で保護を受給しながら日々の生活で使用していたものが壊れたものであり、それを転居に伴って○○へ持参し処分後、新たに購入しているだけであり、転居がなければ単に買い換えが必要であっただけということになる。今回の転居に伴い、○○で生活保護廃止の翌日に新たに○○で生活保護が開始され、○○の生活保護開始時には電子レンジは壊れていたことから、外形上は局長通知第7-2(6)ア(ア)に該当はするものの、○○から転居に係る費用は拠出されており、保護が継続されている状況に変わりない。家具什器は、本来経常的最低生活費の範囲内で、被保護者が計画的に、順次更新していくべきものであり、主の電子レンジの購入は単に新しいものに買い換えたものであることから一時扶助の対象外と判断し、電子レンジの申請も却下したい」としている。
このことに関して、審査請求人は○○での保護廃止の翌日から○○で保護開始されており、生活保護の空白期間は生じていないため、局長通知第7-2(6)ア(ア)が想定する「保護開始時」に当てはまらないと言える。したがって、不支給とした処分庁の判断に誤りはない。
(3) カーテンに係る部分
令和5年○月○日、審査請求人は、処分庁に対して、被服費として毛布及びカーテンの領収証を提出した。これに対して、同月○日に処分庁は審査請求人に対して、カーテンは家具什器費での対応になること、また、既に提出された他の家具什器費の見積りで上限額を超えていることを伝えた。同日、審査請求人は、処分庁に対して、毛布の代金を求める被服費申請書を提出し、同月○日に、家具什器費の申請書を提出したが、その中にはカーテンの代金は含まれていなかった。
したがって、審査請求人が処分庁に対して行った申請には、カーテンの代金が含まれていないため、審査請求人が求める処分の取消しの原因となる処分が存在しないことから、審査請求人の主張は認められない。
(4) 小括
以上のとおり、本件審査請求のうち、温水便座に係る部分は理由があり、電子レンジに係る部分は理由がなく、カーテンに係る部分は処分自体が存在しない。審査請求人及び処分庁のその他の主張については、本件審査請求の結論に影響を及ぼすものではない。
4 付言
(1) 本件処分1に係る申請日について
本件処分1の決定通知書には、「令和5年○月○日付けで申請された生活保護法による保護を次のとおり決定する」と記載されている。しかし、処分庁から提出された資料によれば、同日付け決定については、同年○月○日付け及び同月○日付け申請に対する処分がなされている。したがって、処分通知書に記載されている申請日が誤っている。今後はこうした記載誤りがないよう注意されたい。
(2) 本件処分1に係る不利益処分の内容及び理由について
処分庁は、本件処分1の際に、審査請求人から申請のあった温水便座及び電子レンジに係る家具什器費の申請について検討し、当該家具什器費を給付しないことを決定したとされているが、給付しないこととした旨及びその理由が本件処分1の決定通知書には記載されていない。したがって、当該通知書の記載内容だけでは、申請に対する拒否処分の内容や理由が明確になっていない。
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならず、当該処分を書面でするときは、その理由は書面により示さなければならないとされている(行政手続法(平成5年法律第88号)第8条第1項、第2項)。この趣旨は、行政庁の判断の慎重と公正妥当を担保することによる恣意を抑制する点と、審査請求人に対して不服申立てのための便宜を供与する点にある。
また、生活保護の変更の申請についても同様に書面により通知し、決定の理由を付さなければならないとされている(生活保護法第24条第3項、第4項、第9項)。この趣旨は、行政手続法の趣旨に加えて、決定内容が法令の定めるところにより最も妥当、適正に決定されたものであることを申請者に十分に理解させる点と、生活保護法における保護の趣旨がどこになるのかを、その決定を通じて申請者に理解させ、いたずらに申請者を疑心暗鬼に駆ることなく、申請者と保護の実施機関との間において意思の疎通を図らせる点にある。
ケース記録によれば、処分庁は、令和5年○月○日に審査請求人に対して申請を拒否する処分の内容及び理由を説明したと記録されているが、上記のとおり、当該処分の理由は書面により示さなければならない。したがって、本件処分1は、行政手続法第8条第2項及び生活保護法第24条第4項の規定に違反するものである。
これについて、審査請求人は、○○に対して保有個人情報の開示請求を行い、本件審査請求を行う前に、自身の申請が拒否された理由を書面により知ることになっており、本件において当該手続的瑕疵を主張していない。申請に対する拒否処分の場合、仮に手続的瑕疵を理由に当該処分を取り消したとしても、実体的な違法が存しない限り、再度当該手続が履行された上で申請拒否処分がなされることが予想される。審査請求人が申請した電子レンジに係る費用については、前述したとおり、家具什器費として認められないものであって、当該申請を拒否した処分に実体的な違法が存するとは判断できない。
以上の状況を踏まえれば、本件処分1を、手続的瑕疵を理由に取り消したとしても、審査請求人の権利救済につながらないどころか、かえって紛争を長期化させることになりかねず、審査請求人の権利救済を目的とする行政不服審査制度の趣旨に沿わないことから、本件における手続的瑕疵は取消事由とはならない。
ただし、本件処分1は、理由付記を定めた各種法令の規定に違反するものであり、処分庁において、今後は法令の趣旨を十分に理解し、申請を拒否する処分を行う場合には、その内容及び理由を書面により明確にすることが求められる。
第6 結論
以上のとおり、本件審査請求には理由がないから、「第1 審査会の結論」のとおり、答申する。