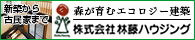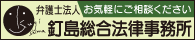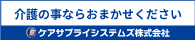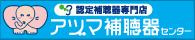本文
令和7年度答申第3号
第1 審査会の結論
本件審査請求には、理由がないので、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第45条第2項の規定により審査請求を棄却すべきである。
第2 審査関係人の主張の要旨
1 審査請求人
処分庁が行った令和6年6月19日付け生活保護変更決定処分2件の取消しを求めるものであり、その理由は、次のとおりである。
光熱費、食料品が全て値上がりしており、生活できない。年金が増えても、その分生活保護費が差し引かれてしまうのは納得できない。増額を求める。
2 審査庁
審理員意見書のとおり、本件審査請求を棄却すべきである。
第3 審理員意見書の要旨
処分庁は、厚生労働大臣が審査請求人宛てに通知した○年○月○日付け国民年金・厚生年金保険年金額改定通知書、○年○月○日付け国民年金・厚生年金保険年金決定通知書・支給額変更通知書及び年金生活者支援給付金振込通知書を踏まえ、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づいて審査請求人が受給する年金を収入として認定し、生活保護費の支給額の基準となる最低生活費から当該年金分を減額することにより、生活保護変更決定処分1(以下「本件処分1」という。)において審査請求人に係る○年○月分の生活保護費の金額(保護の程度)を、生活保護変更決定処分2(以下「本件処分2」という。)において審査請求人に係る○年○月分の生活保護費の金額(保護の程度)を決定した。
処分庁は、年金の収入認定に当たっては、厚生労働省が審査請求人に通知した年間の受給額に基づいて一月当たりの年金額を算出したものであり、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年4月1日厚生省社会局長通知。以下「局長通知」という。)第8の1(4)アの規定により収入認定額を決定した。
処分庁は、本件処分1により生じた差額について、局長通知第10の2(8)の規定に基づいて○年○月の翌月(○年○月)の生活保護費に充当し、本人支払額としたものである。また、本件処分2により生じた本人支払額は、審査請求人の収入が最低生活費を上回った部分について、本人支払額としたものである。
以上のとおり、本件処分1及び本件処分2には、違法又は不当な点はなく、本件審査請求には理由がないから、行政不服審査法第45条第2項の規定により棄却されるべきである。
第4 調査審議の経過
当審査会は、本件諮問事件について、次のとおり、調査審議を行った。
令和7年5月15日 審査庁から諮問書及び諮問説明書を収受
令和7年5月23日 調査・審議
令和7年6月27日 調査・審議
第5 審査会の判断の理由
1 審理手続の適正について
本件審査請求について、審理員による適正な審理手続が行われたものと認められる。
2 本件に係る法令等の規定について
(1) 法第8条第1項は、「保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。」と規定されている。
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第36条第3項及び国民年金法(昭和34年法律第141号)第18条第3項において、年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払うと規定されている。
(3) 国民年金法第26条は、「老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(中略)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。(後略)」と、同法第18条第1項は、「年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め(中略)るものとする。」と規定されている。
(4) 局長通知第8の1(4)アは、「恩給法、厚生年金保険法、船員保険法、各種共済組合法、国民年金法、児童扶養手当法等による給付で、1年以内の期間ごとに支給される年金又は手当については、実際の受給額を原則として受給月から次回の受給月の前月までの各月に分割して収入認定すること。なお、当該給付について1年を単位として受給額が算定される場合は、その年額を12で除した額(1円未満の端数がある場合は切捨)を、各月の収入認定額として差し支えない。」と規定されている。
(5) 局長通知第10の2(8)は、「最低生活費又は収入充当額の認定を変更すべき事由が事後において明らかとなった場合は、(中略)当該事由に基づき扶助費支給額の変更決定を行えば生ずることとなる返納額(確認月からその前々月までの分に限る。)を次回支給月以後の収入充当額として計上して差し支えないこと。(後略)」と規定されている。
(6) 医療扶助運営要領(昭和36年9月30日厚生省社会局長通知)第3の2(2)は、「要保護者が医療扶助のみの適用を受けている者である場合には、(中略)当該要保護者の属する世帯の収入充当額から当該世帯の医療費を除く最低生活費を差し引いた額をもって本人支払額とすること。」と規定されている。
3 本件処分1及び本件処分2の妥当性について
処分庁は、法第8条第1項に基づいて、審査請求人が受給する年金を収入として認定し、生活保護費の支給額の基準となる最低生活費から当該年金分を減額することにより、別紙のとおり、本件処分1及び本件処分2において、審査請求人の○年○月分及び○年○月分の生活保護費の金額(保護の程度)を変更した。
厚生年金保険法第36条第3項により、老齢厚生年金は、「毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月分までを支払う。(後略)」と規定されていることから、○年○月分及び○年○月分の年金は、○年○月に審査請求人に入金され、○年○月分及び○年○月分の年金は、○年○月に審査請求人に入金される。また、審査請求人が○年○月に65歳の誕生日を迎えたことから、国民年金法第26条は、「老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(中略)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。(後略)」と、同法第18条第1項は、「年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め(中略)るものとする。」と規定されていることから、審査請求人は、○年○月から老齢基礎年金等を受給することになり、同条第3項により、老齢厚生年金と同様に入金される。
年金の収入認定に当たっては、局長通知第8の1(4)アにより、「1年以内の期間ごとに支給される年金又は手当については、実際の受給額を原則として受給月から次回の受給月の前月までの各月に分割して収入認定すること。」と規定されていることから、処分庁は、生活保護費に係る収入認定において、審査請求人の○年○月入金分の年金(○年○月分及び○年○月分の年金)を○年○月及び○年○月の収入として認定し、○年○月入金分の年金(○年○月分及び○年○月分の年金)を○年○月及び○年○月の収入として認定した。
○年○月○日付け保護決定調書(○年○月分)によると、審査請求人は、生活保護の種類のうち、生活扶助のみを受給していたことが確認できる。また、○月の審査請求人の収入額は、最低生活費を上回っていることから、処分庁は、○月分の生活保護費からは、これまで支給していた生活扶助を支給しないこととしたため、審査請求人が医療を受け、医療扶助の申請が認められた場合には、医療扶助のみを受給することになる。したがって、処分庁は、医療扶助運営要領第3の2(2)に「要保護者が医療扶助のみの適用を受けている者である場合には、(中略)当該要保護者の属する世帯の収入充当額から当該世帯の医療費を除く最低生活費を差し引いた額をもって本人支払額とすること。」と規定されていることから、審査請求人の収入充当額から最低生活費を差し引いた額を本人支払額とし、これに○年○月分の生活保護費の過支給額を加えて、○年○月分の本人支払額を決定した。これは、審査請求人が医療を受けた場合には、要した医療費のうち、本人支払額とされる医療費分については、医療扶助費として処分庁が負担するのではなく、審査請求人が直接医療機関へ支払うよう求めるものである。
(1) 本件処分1の妥当性について
○年○月○日付け国民年金・厚生年金保険年金額改定通知書によると、審査請求人の老齢厚生年金の○年○月入金分(○年○月分及び○年○月分の年金)は、○円(月額)(○円(年額))であったが、○年度の年金額の改定に伴い、○年○月入金分(○年○月分及び○年○月分の年金)からは、○円(月額)(○円(年額))に改定された。そのため、処分庁は、既に支給済みであった○年○月分の生活保護費について、遡及して収入認定額を○円(月額)に変更した。
審査請求人の最低生活費は、○円(月額)であることから、○年度の年金額の改定前に審査請求人に支給されていた生活保護費は、最低生活費から老齢厚生年金を引いた○円(月額)であったが、○年度の年金額の改定後(○年○月入金分(○年○月分及び○年○月分の年金))からは、老齢厚生年金が○円(月額)増額したため、審査請求人に支給されるべき○年○月分の生活保護費は、○円であり、○円生活保護費を過支給していることが判明した。
局長通知第10の2(8)は、「最低生活費又は収入充当額の認定を変更すべき事由が事後において明らかとなった場合は、(中略)当該事由に基づき扶助費支給額の変更決定を行なえば生ずることとなる返納額(確認月からその前々月までの分に限る。)を、次回支給月以後の収入充当額として計上して差し支えないこと。(後略)」と規定されていることから、処分庁は、○年○月分の生活保護費の過支給額を次回支給月の○年○月分の本人支払額に充当することを決定し、審査請求人に令和6年6月19日付け保護決定通知書(○月分)により通知した。
(2) 本件処分2の妥当性について
○年○月○日付け国民年金・厚生年金保険年金決定通知書・支給額変更通知書及び年金生活者支援給付金振込通知書によると、審査請求人は、○年○月に満65歳を迎え、○年○月分の年金(○年○月入金分)からは、老齢厚生年金○円(月額)(○円(年額))、老齢基礎年金○円(月額)(○円(年額))及び年金生活者支援給付金○円(月額)を合計した○円(月額)が給付されることとなったため、処分庁は、○年○月分の生活保護費に係る収入認定額を変更した。
審査請求人の収入額○円(月額)が最低生活費○円(月額)を上回ったことから、処分庁は、○年○月分の生活保護費からは、これまで支給していた生活扶助を支給しないこととし、局長通知第10の2(8)の規定により、収入額と最低生活費との差額○円を本人支払額とした。その上で、処分庁は、これに本件処分1により○年○月分の本人支払額に充当することとした○円を加え、○円を同月分の本人支払額とすることを決定し、審査請求人に令和6年6月19日付け保護決定通知書(○年○月分)により通知した。
(3) 小括
本件処分1及び本件処分2は、法令等の定めるところに従って、適法かつ適正に行われたものであり、違法又は不当であるとはいえない。
4 付言
審理手続において、処分庁は、本件処分1及び本件処分2により、○年○月から本人支払額が発生することについて、審査請求人に口頭で説明したが、説明した旨をケース記録票に記載していなかったことが確認されている。
審査請求人は、本件処分1及び本件処分2により、これまで受けていた保護の程度から大きく変更され、新たに本人支払額という制度が適用されることになったのであるから、処分庁は、審査請求人の制度の理解を促すため、丁寧に説明することが望まれ、制度の説明をしたのであれば、その事実をケース記録票に記載すべきであった。
ケース記録票は、保護決定の根拠や適用の過程を記載するものであり、不服申立てや訴訟においては、重要な挙証資料になる。処分庁は、この点も踏まえ、ケース記録票の記載について、より適切な運用がなされるよう留意されたい。
第6 結論
以上のとおり、本件審査請求には理由がないから、「第1 審査会の結論」のとおり、答申する。