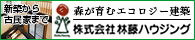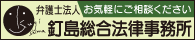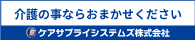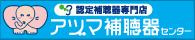本文
令和6年度第2回県立図書館協議会の開催結果について
1 日時
令和7年2月13日(木曜日) 13時30分~15時25分
2 開催場所
県立図書館3階ホール
3 出席者
委員7名出席、事務局8名
4 傍聴人
0名
5 議事
(報告事項)
(1)令和6年度事業の実施状況について
(2)県立図書館サービス評価について
・令和6年度図書館サービス評価目標の達成状況
(審議事項)
(1)県立図書館サービス評価目標について
・令和7年度図書館サービス評価の目標設定(案)
(2)令和7年度主要事業(案)について
発言の概要
(報告事項)
(1)令和6年度事業の実施状況について
(2)県立図書館サービス評価について
・令和6年度図書館サービス評価目標の達成状況
(委員)
動画の発信は好評ですか。
(事務局)
最初は閲覧数が伸びるのですが、その後がなかなか続かない。一回注目を集めればいいのですが、なかなか難しい。職員が少々はじけて撮影した動画、動物を利用したもの、時として真面目なものなど、いろいろ織り交ぜながら制作していきたいと思っています。職員もだいぶ慣れてきましたけれど、本当はとても大変な作業で、それでも前向きに撮影してくれるようになってきていますので、引き続き発信できればと思っているところです。
(委員)
〇〇委員と私はビブリオバトル県大会に参加させていただきましたけれども、いかがでしたか。
(委員)
実は、高校の図書館部会、地区幹事会から、ビブリオバトルに関しまして要望を二つほど伺っており、今日この場でお伝えしていただきたいと承っています。まず要望1として、以前のように大学と高校の大会は別開催にしてほしい。理由は、大人数の発表を聞くのはかなり持久力が必要で、最終的に五時半くらいに終わって、11月開催ということもありかなり暗くなってしまい、遠方から来ている高校生もいますので、そこから帰ることを考えるとかなり負担が大きかった。もう一つは、高校と大学で大会のルールが違っていて、特に高校生に関しては、本1冊と本人のみと指導しているのに対して、大学生はかなりパフォーマンスに走ってしまっていて参考にすることが非常に難しく、困惑して見るだけになってしまったと、承っています。
要望2として、申込方法について検討してほしい。理由としてコロナ禍以降、群馬県大会各高校から県立図書館に直接申込みになっています。しかし、今回ある高校が校内大会でチャンピオンを決めて県立図書館に申し込んだところ、定員に達していたということで断られてしまったそうです。生徒はショックを受けたということでした。実際は、その後他校でキャンセルが出たのでその生徒は参加することができたらしいのですけれど。校内で指導があって、校内大会をしてとなると、している間に締め切られてしまう可能性がある。申込方法について検討してほしい。もう一つ補足として、地区大会を成り立たせるほどの発表者数を集められない地区や学校も存在するので、地区大会を必須にせずに、選考方法に融通が利くようにお願いできたらという要望を承っております。
(事務局)
委員から御指摘のあったとおり、ルールが違うので観ている方としても困惑してしまう、それは私も一個人として思ったところですので、御意見を承った上で、来年度についてはまた開催方法を検討したいと考えています。申込方法についても、地区によってやり方がいろいろ違うという情報を承っていますので、考慮した申込方法を考えたいと思っております。
(委員)
素朴な質問ですけれども、先ほどあった読書推進に役立つボードゲームに興味を持ったのですが、具体的にどういうものなのか教えていただけますか。
(事務局)
私も実はボードゲームを知らなかったのですが、今、全国的に図書館でこのボードゲームの活用が広がりつつあるということです。知育だけではなくて、読書推進や教科学習の展開にも有効であると言われています。ゲームはいろいろな種類があるようで、承知しているのは世界4か国で実際に行われているルールをもとにしてゴミの分別について考える協力型のゲームでして、これは社会科や理科での環境学習ですとか、今流行りのSDGs、そういったものに適していると言われております。「みんなで本をもちよって」というゲームについては、各プレイヤーが実際に本を1冊持参して遊ぶゲームで、お題カードの質問に対してその本の中の文章を引用して回答する、楽しみながら短時間に集中して活字や文章と向き合うことができると言われています。そういったものを導入していければと考えています。
(委員)
具体的なイメージがわかなかったのですが、オンラインのゲームではなくて、実際のゲームなのでしょうか。
(事務局)
オンラインではなくて、物を取り囲むような形です。
(委員)
何人ぐらいで参加するゲームなのですか。
(事務局)
物によって違うのですが、3人から6人とか、2人から8人とか、ゲームの種類によって違うようです。
(委員)
そのゲームは、日本のゲームなのですか。それとも海外のボードゲームメーカーのものですか。
(事務局)
発祥はもともと海外らしいのですが、日本で手に入るものは日本語で書いてあるということです。
(委員)
内容は教育的なものなのでしょうか。
(事務局)
読書に繋がるように、考えられているということです。
(委員)
それを県立図書館で借りることはできるのですか。
(事務局)
まずはいくつか購入して、この学習支援図書セットの一部として貸し出しすることについて、学校の先生方に御意見を伺いたいと思っていたところです。
(委員)
その1セットはいくらぐらいするものですか。
(事務局)
値段は物によってばらばらです。手元にある資料で一番安いのは2,000円ぐらいで、少々高いものですと5,000円です。
(委員)
報告2の令和6年度群馬県立図書館サービス評価目標の達成状況の図書館等職員研修ですが、やはり私たちもオンラインで慣れているというか、オンラインですと参加が容易だけれどなかなか対面になると一日や半日、仕事から離れなければいけないということで参加が難しくなるのは、よく理解できます。ハイブリッドにするなどいかがでしょう。
(事務局)
対面の良さを活かしつつ、どうしても来られない方にはオンラインで御視聴いただけるようにはしたいと思っています。今年度はそこまで思いが至らなくて、とにかく、対面が意見交換等できるのではないかと思い、顔の見える環境を作ったり、講師から何か話しかけていただいたり、質問していただいたり、そういうことができることから「対面がいいのではないか」と軽く言ってしまったので、来年度は上手にハイブリッドなど活用していければと考えています。
(委員)
イベントのアナウンスの方法についてです。ブックフェスが大変盛況で、私も参加させていただいたのですが、街中がものすごく混みあっていて、これだけ本に興味を持っている人がたくさん集まるのだということで、感心したところです。そのお知らせを依頼されるのに、図書館からメールが届きまして、学校に流すようにということだったのですが、県立の図書館なので委員に個人的にメールでお知らせしてほしいという形ではなくて、例えば県教育委員会に連絡を取り市町村に流してもらうという形で、ここでしたら市教育委員会から各学校にこのお知らせの連絡がいくと思います。前橋ですと「すぐーる」というアプリが使われていまして各家庭に配信される形がとれると思うので、御検討いただけるといいのではと思いました。今回また、みやま文庫のお知らせが来たのですけれど、学校の前情報として「保護者からのメールは学校では開けない」というルールがあり、ウイルスが付いたりするといけないというセキュリティの関係がありまして、ただ最近になって「開けます」という話でしたので、今回は直接、学校に転送させていただきました。一保護者から学校に送るというと拒否される学校があるみたいなので、御検討いただけると有り難いです。
(事務局)
広報に関しては、本当に広く広報しないとなかなか行き渡らないという思いから、言葉は良くないのですが、使える手段はあらゆる手段を使って拡散をしたいと考えているところです。その一環として委員の皆さんにも広報の御協力をお願いしたところなのですが、委員のお話にあったように県教育委員会にも当然情報は提供してありますし、いろいろな媒体、手段を使って、もちろん重なってしまう部分もあるのですけれど、御無理の無い範囲でお願いしたいという思いでメールを差し上げてしまった次第です。少し配慮が足りなくて申し訳なかったのですけれども、これからもいろいろ重なってもいいからとにかく届かないことには意味がないので、そういった広い広報を心がけていきたいと思っているところです。
ブックフェスについては委員にも来ていただいて御覧いただいたと思うのですが、本当に好評でして、まだまだ広報の余地があったのではないかと考えているところです。
(委員)
2ページに書いてある、電子書籍の使い方で高校に行ったと思うのですが、実際にこちらを利用したことによって貸出冊数にどんなプラスがあったのか。こちらとしては、使ってもらいたいのだけれども、それをどうするかというきっかけがなかなかないと思うので、立地的にはなかなか県立には来られない学校がそれを使うことによって、こんなふうに授業に役立ったというところがあれば教えていただきたいです。
(事務局)
この学校に出前授業をして、電子書籍の使い方について話をしたのが即、貸出冊数に繋がっているかどうかというのは、一概には言えず、分かりかねるところなのですが、先ほど御覧いただいた参考資料4、電子書籍の閲覧回数の変化を見ますと、特に今年度に入ってから8月以降、閲覧回数が4桁で、一桁増えています。出前授業との直接の関係は、ここでは申し上げられないのですが、高校での一括登録や地道な広報が実を結んでいるのではと思っています。確かに山間地では蔵書の冊数にも限りがありますし、予算も限られているので、県教育委員会の高校教育課とも相談しながら、中山間地の高校からまずはやっていきましょう、ということで〇〇高校の一括登録等に繋がったところです。今後も同じようにやっていければ、本に対するアクセスが均等に近づいていけるようになるのでいいのではないかと考えております。
(審議事項)
(1)県立図書館サービス評価目標について
・令和7年度図書館サービス評価の目標設定(案)
(委員)
(2)の電子書籍サービス閲覧数をサービス評価目標に入れるというのは、これまでの中で提案があったことですのでこちらに入れていただくのはいいと思います。一万回という目標値の根拠はなんですか。
(事務局)
14ページの「目標値設定の考え方」に記載がありますとおり、サービスを開始した令和5年1月から6年の12月までの月平均閲覧回数が約760回でしたので、それの10%増という目標を掲げて数字を丸めて1万回という数字にしています。
(委員)
電子書籍の購入には今どれくらい予算を充てているのですか。
(事務局)
今年度は697万5000円になっております。
(委員)
来年度も同じくらいの金額でしょうか。
(事務局)
同金額で要求を出しておりますので、見通しとしては同額を見込んでおります。
(委員)
10%増を目標とするということで、こちらはまだ伸びしろのある分野かと思います。(3)ビブリオバトルの参加者数で、関連行事というこの関連とはどんなものでしょう、ビブリオバトルそのもの以外にも何か含まれる行事があるような感じですが、どういうものを含めるのでしょうか。
(事務局)
資料15ページの目標値設定の考え方にありますとおり、まずビブリオバトルの高校生大会の参加者数を80人と見込みまして、それ以外に出前授業や出張研修でビブリオバトルのすそ野を広げるための授業や研修でお知らせしているものですから、そういったものもビブリオバトルに関連した事業等の人数や参加人数を含めた形で指標としたということです。大会の本体だけではなくて、それ以外にビブリオバトルを広げる取り組みを含めた、ということです。
(委員)
これは県立図書館主催のイベントでということで、全く県立図書館と関係なく小学校とか中学校でやっているものは把握できないわけですか。
(事務局)
それは入れてないです。
(事務局)
15ページの7年度の目標にもありますが、出前授業や出張研修でビブリオバトルを行った時も、その児童・生徒の人数もカウントするという考え方です。なぜ、こう広げたかというと、昨年度の第一回、前任の委員から、「例えば野球の甲子園は甲子園だけに出ている生徒だけではなくて地区予選に出ているそういう裾野の大きい広がりのある大会なので、ビブリオバトルも同様に、地区の予選をしている地区予選とか校内選考の参加者数も考慮してください。」というお話がありました。それで調べたところ、校内選考の方法にもいろいろあり、先ほど委員からのお話にありましたとおり、地区大会をやっていないところもあり、全体を拾うのはなかなか難しいので今回の案で試行してみて、来年度はこのやり方でビブリオバトル関連の裾野の広がりをとらえてみようという考え方で設定をさせていただきました。
(委員)
出前授業・出張研修では必ずビブリオバトルが行われているということですか。
(事務局)
ビブリオバトルを知らないお子さんたちに、例えば「ビブリオバトルとはこういうものですよ。それでは、今日この授業で皆さんやってみましょう。」と言って、挑戦してもらうというイメージです。
(委員)
その人数は県立図書館で数えて把握しているのですか。
(事務局)
県立図書館職員が伺って一クラス何名だったと人数をカウントする形になります。
(委員)
県立図書館が特に関わっていないところで、小学校や中学校の授業で行っているものは把握できないけれど申告してもらうことはないのでしょうか。
(事務局)
それはこの数には入っていないです。今、特別館長が言ったとおり、これでやってみて他にいい方法が、例えば、今委員がおっしゃったようなやり方がもし良いとなれば、そういう数字も集めた上で目標を設定しなおすことも可能性としてはあると思います。
(委員)
いかがでしょうか。
(委員)
県立図書館の案でいいと思います。
(委員)
来年度のビブリオバトルについては先ほど、委員からも御要望がありましたのでやり方を考えていただくことになります。(9)の学習支援図書貸出冊数は未定、要検討ということですが、これはこの協議会ではどういう発案をすればよろしいのでしょうか。
(事務局)
達成率が低い二つの項目のうちの一つでしたが、目標値6,500冊に対して現在進捗率が58.4%、6割を切っている状況です。資料20ページに、一人一台端末が行き渡るにつれて調べ学習等においても端末を使う機会が増えているという背景、それだけが原因とは当然思いませんが、学習支援図書の役割も変わってきているのではないかと考えております。それで、対応としてボードゲームを先ほど御説明しました。ではこの目標値を設定する時に今年度の目標値がここにあるとおり6,500冊ですけれど、また継続で6,500と来年度も掲げるのがいいのか、あるいはもう少し現状を反映して目標値は下げたうえで、ボードゲーム等新たな取組を進めていくのがいいのか、委員の皆さんから御意見をいただきたいと考えた次第です。
(委員)
ボードゲームはこの指標の中に入るのですか。
(事務局)
指標に入れるべきかどうかも併せて御意見いただけますか。
(委員)
貸出冊数としているけれども、ボードゲーム含むとするかどうか。
(事務局)
外書きにするとか、表記を分かりやすくするとか、冊数とボードゲームとするか、合わせてしまうのも少し難しいのではないかとは思ったのですが。
(委員)
選択肢としては、目標値を下げるというのと。
(事務局)
目標値を同じにするか、若干下げるか、合わせてなのか。
(委員)
そこにボードゲームを入れてカウントするか。ボードゲームの利用は主に小学校・中学校ですか。
(事務局)
はい、そうです。
(委員)
先ほどのボードゲームのお話ですと、書籍とは少し違うと思ったので、この中に含まれるのは違う気もします。お借りするとしても例えば4セットとか、お借りした時に、本ではないので例えば出前授業の回数ですとか、もしボードゲーム以外のカードゲームとかいろいろなものが付随するものがあれば、そういうところでひとまとめにして貸出数でまとめていくのが良いのかなと思いました。
(委員)
ボードゲームはすごく魅力的です、今時の子ども達にとってみれば。本当にやってみたいと思う子ども達も多いと思います。できれば職員の負担を減らす意味で、出前授業で職員も一緒にセットでつけてくれるとこちらはすごくありがたい。全部先生が調べて、やって、それで子ども達にやらせるという負担感を考えてしまうので。職員が来ていただいて講師としてやっていただけると更に学校は声を掛けやすいと思います。
(事務局)
出前授業のメニューの一つにボードゲームの項目を加えるようなイメージでしょうか。
(委員)
職員の負担という話に付随してですが、昨年度からビブリオバトルでお世話になっているのですけれども、昨年、県立図書館に来ていただいて、担任が一緒になって三名で見本を見せたんです。本校では今年も実施したのですが、去年やった職員が一人残っていたのでとてもやる気で、残り二名の職員は余り本に興味の無い担任だったのですが、すごく感化されて一生懸命やって、とてもいい発表、見本が見せられました。去年、市内で私から周知して、何校か参加したところがあったと思うのですが、今年見たら、うちの学校だけで、去年やってみた学校は今年続かなかった。やはり職員がやるというのは負担です。私は、「やってね」という感じで盛り立てて、実施してもらったりしたのですけれど、継続するには負担感がないといいので、職員とセットで一緒にやってもらえる出前授業が一番いいと思います。
(委員)
学習支援図書の貸出冊数の中にボードゲームを含めるかどうかについては御意見いかがでしょうか。
(委員)
先生方の話を伺って、私もそうだろうなと思いました。(10)にあります学校に対しての出前授業や出張研修に、ボードゲームを追随させる形にして、出前授業や出張研修の時にはビブリオバトルの説明をし、ボードゲームでのアドバイスもし、そこで実践もし、という感じのセットで、一度図書館の方が来てくれるとビブリオバトルもボードゲームも全部を教えてもらえる感じにするといいと思ったのですけれども。冊数はもし残した方が良ければセットの冊数はまた別で目標を立てるという形がいいと思います。前回、指標をあまりころころ変えない方がいいという御意見があったようなので達成度がなかなか難しくても、指標はあくまで長期的に推移を見ていく事案かと思いました。
(委員)
いかがでしょうか。まず、ボードゲームはやはり本とは違うのでここに含めない方がいいのではないかということと、達成状況は厳しいのだけれども、そこだけを見るのではなくて推移を見ていくということで目標値は変えないでこのままでいいのではないかというような御意見をいただいていると思うのですけれど。では(9)については協議会としてはそういう意見が出たということでいかがでしょうか。
(事務局)
貴重な御意見をありがとうございます。そうすれば、ボードゲームにつきましては出前授業のメニューに加える方向でこれから検討したいと思います。また、指標については長期的にという話は確かにそのとおりですので、その御意見を踏まえまして7年度の目標は設定したいと考えております。また、目標値を安易に下げるべきではないと考えておりますので、そういったことを踏まえて7年度も設定したいと思います。
(委員)
(10)の訪問というのは、図書館の職員が現地に行って、ボードゲームをやる、ビブリオバトル等の指導をするということですが、図書館にとって負担はあるのですか。
(事務局)
(10)につきましては、新たな取組です。資料20ページに書いてありますけれども、目標値設定の考え方にありますとおり、市町村立図書館、学校図書館等に対してこれまで以上の支援を行うということで設定した指標です。「県立図書館のあり方検討報告書」にも記載されておりますので、力を入れていかなくてはいけないという思いから設定しました。確かに新しく取り組む事なので負担がないとは言いませんが、こういった取組は非常に県域の中核館として重要であるという認識でおりますので、目標達成に向けて頑張っていきたいと考えているところです。
(委員)
学校に行く時は、県立図書館の職員は何人くらいで行くのですか。
(事務局)
一人の場合もありますし、二人の場合もありますけれど、ここで言っている訪問というのは、今までやってきた出前授業とはまた別のイメージのものも含まれていて、いろいろな業務に関する情報交換をしたり、あるいはずっと県立に聞きたかったけれど、なかなか聞く機会がなかったという意見を吸い上げたりとか、いわゆる顔の見える関係を築いていく機会になればと考えています。
(委員)
出前授業というのは図書館だけではなくて県のホームページからいろいろなものに対して申込みをして、そして日程調整をして来ていただくという要望に基づいてやるものと、図書館として売り込んでいく、そういうものはあるのですか。
(事務局)
従来やってきたのはビブリオバトルをやってみようとか、百科事典の使い方について、メニューの決まったものですけれども、ここではメニューが決まっているものだけではなくて、もう少し幅広のもの、出前授業という言葉が良くないのかもしれないのですが、いずれにしても図書館が出ていくというイメージのものでして、特段テーマを限定しているものではないです。
(委員)
要望で行うだけではなくて図書館側として、「行きますよ」ということを宣伝したりするものですか?
(事務局)
なかなか、要望は出てこないものもありますので、どちらかと言うと、一年では無理かもしれないのですけれど、全域を隈なく回れるようにできればいいと思っているところです。こちらから出向いて行くという感じです。
(委員)
先ほどの話ですと、職員が来てやってくれるというものであれば、学校としてはウェルカムだということなので、もっとできるのではないかというような気もしましたが、今回、新規の目標設定ということですので、やっていただいて、様子を見ていく感じとなりますでしょうか。いかがでしょうか、この目標値の設定については、22ページまでに説明資料がありますけれども、御提案を協議会としてお認めしてもよろしいでしょうか。
では、県立図書館サービスの評価目標設定について事務局案のとおりで、未定のところは今後決定いただくということで協議会委員の意見といたします。
(事務局)
本日いただいた御意見をもとにして決めたいと思っております。安易に目標値を下げたりはしないようにしていきたいと考えております。
(委員)
この部分については我々の意見を踏まえて、決定していただくということで、それ以外については御提案の案をお認めするということとしたいと思います。
(2)令和7年度主要事業(案)について
(委員)
事業案の中で、特に令和7年度に力を入れたいものはありますか。
(事務局)
全部ですと言いたいところですけれども、まだまだ図書館サービスの周知が図られてない部分も多いです。そういったものを解消する取組はまず進めていかなくてはいけないと思っております。図書館に足を運んでいただく、本を借りていただく、読書に興味を持っていただく、そういった取組は地道に続けていく必要があると考えています。
それからデジタルの推進ということで、電子書籍サービスやデジタルライブラリーの整備については、引き続き力を入れていきたいと考えています。やはり県域の中核館として各図書館のお役に立てるような研修の企画立案ですとか、指標からは外れますが、協力レファレンスにも力を入れていきたいと考えています。広い意味での支援、あるいは研修等の人材育成にも引き続き力を入れていきたいと考えています。
(委員)
県から図書館に配分される予算は例年どおりなのですか。
(事務局)
なかなか財政状況が厳しい折ですが、来年度については、書籍の購入等に関しては同様の予算をいただけることになっております。若干、削られた部分もあるのですが、読書推進に係るものについてはおおむね同じだけ確保できたと思っています。
(委員)
24ページの読書活動支援1000冊プランはこれまでもあった活動なのですか。
(事務局)
継続事業です。
(委員)
令和7年度はこの4町村を重点支援ということなのですか。
(事務局)
図書館が未設置の町村を支援するための事業です。
(委員)
非常に人材育成は大切だと思います。各公共図書館などでは図書館職員が非正規も多いと聞いていますが、県立図書館では司書採用はどういった対応をとられているのでしょうか。
(事務局)
県立図書館でも非正規、いわゆる会計年度任用職員が20数名働いております。全員に司書資格があるわけではないのですが、司書資格を持っている人もいます。一回採用されると基本3年は働けるのですが、こういう業務ですので、いきなり全員を新しくするというのは難しく、ある程度ベテランもいてもらわないといけない部分もあります。とはいえ、組織として新陳代謝も必要な場合もあるでしょうから、いろいろな事情を勘案しながら対応はしていきたいと思っています。今いる20数名には早番・遅番や土日出勤など、うまく組み合わせながら働いてもらっているところです。エピソードの「利用者の声」で窓口でのカウンターでの応対がすごく良かったなど、利用者目線に立って対応してもらっているといつも感じているところでして、継続して引き続き満足していただけるような対応をしていってもらいたいと思っているところです。
(委員)
非正規の図書館職員に対しても研修、スキルアップの機会というのは十分提供されているのですか。非正規は5年まで、最長4年でしょうか。
(事務局)
県は3年です。
(委員)
3年非正規をやるとそこで辞めないといけないということですか。
(事務局)
ただ再度同じ人を雇用することを妨げないということですので、公募した結果、他に手が挙がらなかったり、継続で手を挙げていただいてと、いろいろな状況があると思うのですが、そのまま、またお願いすることもあり得ます。
(委員)
非正規でも10年も勤め続けることができるということでしょうか。
(事務局)
できると言い切ることは難しいですけれど、そういう場合もあり得るということです。原則3年で、3年ごとに公募し直しますので、その時点で他に手が挙がらなくて、公募した結果、その人がまた手を挙げれば、他にいないから継続となります。
(委員)
非正規を正規に雇用する仕組みはあるのですか。
(事務局)
正規になるには県の職員の採用試験を受けて合格しないと正規になれないです。ただ、今は、司書枠での採用をしていないので一般行政事務で採用されることになるため、その後、図書館配属になるかどうかはまた分からないです。
(委員)
群馬県としては司書採用というものはありますか。
(事務局)
現在、していないです。
(委員)
ずいぶん前から止めたのでしょうか。
(事務局)
止めた訳ではないのですが、やっていない状況が継続しているということで、必要があればまたそういう採用をすることになるとは思うのですが。
(委員)
司書の位置付けというのは、各大学でも公共図書館でも少し難しい状況とは聞いております。
(委員)
第1回図書館協議会の時に職員構成の内訳を教えていただき、かなりの割合で司書がいたような気がするのですが、今、一般行政事務でも働いていることが分かりました。
(事務局)
図書館職員全部で会計年度任用職員含めて44人いるのですが、その中で、司書資格のある人が21人で、約半分ということです。ただ、会計年度任用職員の中で司書資格のある人が正規になるということはできない状況にあります。
(委員)
最初の動画を見せていただいて、今回すごく県立図書館が変わったという感じがしていて、職員の前向きな姿勢がすごく感じられる。自分から学校や図書館、地域に出ていくという姿勢もはっきり出されていてすごく期待しています。頑張ってください。
(委員)
今のショート動画の件で本当に楽しい動画を見させていただいたと同時に「これ何ですか」と調べてくれる、図書館のそういう使い方もできるということを初めて知りました。周知したいと思うのですが、確かに簡単にクリックすれば見られるとは思いますけれど、そもそもホームページを開くこと自体が本当に本に興味のある人なのだと思います。興味がなく、なかなか足を運ばない人にこそ見てもらいたいと思ったのですけれど。お金がかかることだと思うのですが、できれば大型のスクリーンに映し出すとか、県庁に無料でそういうことができるところはないでしょうか、まず発信して皆の目に触れて、「あれ何だろう」、「県立図書館はそういうことができるのか」、「他も見てみよう」というようなきっかけがどこかであるといいと感じました。
(事務局)
知らないと見ていただけない。非常にそこは難しいところです。これから何か知恵を絞ってその辺は克服していきたいと考えています。
(事務局)
先ほど、委員がいわゆるレファレンスサービスについて、もう少し知りたいということだったと思うのですけれど、どこの図書館も実はやっている基本的な図書館のサービスの一つです。〇〇図書館でも非常に力を入れて専任の職員を置いていますので、ぜひ御利用いただければと考えています。図書館のことを知ってもらう取組は非常に重要ですが、まずは県職員に知ってもらう。レファレンスサービスについて県職員はほとんど知らないと思います。職員はいろいろなことで調べものが必要です。例えば議会で質問されるのでいろいろ調べなくてはいけない、部長や課長から聞かれるけれども手元にある資料は限られています。その時に図書館の資料は非常に活用できると思うのですが、残念ながら図書館で何か調べようという職員は、私も含めて余りいないと思います。資料の4ページ、情報発信に記載されていますが、「群馬県庁ポータルサイト」という県職員向けのサイトに、「図書館は皆さんの仕事で役立つ」というのを発信して実際に使い方も示さないとなかなか使えないだろう、使ってもらえないだろうということで、取組を始めたということです。まずは身内からと。非常に重要な取組でして、図書館のサービスというのは人とお金でできています。それはどこが握っているかというと、やはり県庁の中にいる財政を担当している人とか人事を担当している人です。そういう人に図書館の取組を理解してもらうのは、図書館の味方になってもらうというのが重要です。図書館は重要だな、自分達の仕事にも使えるし、県民の皆さんにも役立っているということを、まずは身内から知ってもらうため、こういう取組を始めています。また県議会議員に対しては、例えば国立国会図書館は国会議員の政務調査のためにあるというのが一つの大きな機能なので、そう考えると群馬県立図書館も議員の活動にもっと使ってもらっていいのではないかなということです。少数の議員には日ごろ来ていただいているのですけれど、もっと多くの方、多くの議員にも使ってもらいたいということで議員にもお知らせをして地道な活動をしておりまして、また、職員には当然、家族や関係者がいますのでそういうところから口コミなり、広げていければと考えております。一般的にホームページで図書館の取組をお知らせするのはあるとは思うのですが、地道な努力と両面で取り組むことが必要かと思いますので、引き続き御支援をいただければと思います。
(委員)
令和7年度主要事業案について非常に大事な取組が掲げられていますので、ぜひこちらを進めていただければと思います。当協議会といたしましてはこの事務局案のとおりお認めするということでよろしいでしょうか。
(委員)
次第4の意見交換ということで、当協議会の役割として図書館サービスについてこれまでもいろいろな意見をいただいているところですが、館長に意見を述べることとされておりますので、この機会に委員の皆さまから県立図書館について忌憚のない御意見をいただければと思います。
(委員)
お願いですけれども、私もこの委員として周知していきたいということで、校長会や図書館教育主任会などで、ビブリオバトルとか電子書籍、出前授業等を周知させていただいていたのですが、電子書籍も登録のことなどで、小学生にももしかしたら調べ学習で役立てることができるのではないかと思うと、私が話をするよりも実際に来ていただき出前授業で電子書籍サービスについて教えていただけると、より良いのではと思いますので、ぜひ校長会の時に来て説明していただけると、有難いと思っております。
(委員)
図書館は非常に地味な存在のようですが、多くの人がインターネット上でいろいろな情報に簡単に触れ、事実か確認されていない情報を真に受けてしまうとか、非常に知識が偏ってしまったり、オンラインで相手が見えないから誹謗中傷したりなど、オンラインにはメリットがあるものの、事実にないことを暗に発言するというような弊害も非常に指摘されている中で、やはり図書館というのは信頼できるまた価値ある情報を発信するという、地域にとっての重要な知の基盤であると思います。オンラインと対面等両方活用しながら、ぜひ地域の人々の知的な活動を支援していただければと思います。
本日は皆さんに活発な御意見をいただき、充実した協議会を運営することができました。心より御礼申し上げます。県立図書館におかれましては、委員の意見を真摯に受け止めていただき、引き続き県民サービスの向上に取り組んでいただければと思います。