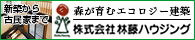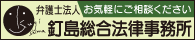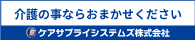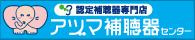本文
令和6年度第2回群馬県文化審議会の概要(通算27回目)
更新日:2025年3月4日
印刷ページ表示
1 開催日時
令和7年2月7日(金曜日)9時30分~11時30分
2 場所
群馬県庁29階294会議室(オンライン参加含む)
3 出席者
委員10名
4 議題及び主な意見
(1)会長、副会長の選出について
会長に松原委員、副会長に熊倉委員が選出された。
(2)部会に属する委員の指名について
青野委員、朝倉委員、志尾委員、友岡委員、牧野委員を部会委員として決定。
(3)令和7年度文化振興関連主要事業について
文化振興課より、概要について説明を行った。
質問回答
【やるぞ!バズるぞ!上毛かるたプロジェクト】
(委員)
- 「知事がみんなの夢を叶えます」プロジェクトにおいて、100万円を上限に、みんなのためになる喜ぶような夢を実現できるようにサポートとあるが、イメージが湧かない。
(文振課)
- 県大会で優勝したチームについては、地域の皆のためになるものについて考えてもらう。例えば、中学生であれば、部活で「こんなものがあれば良い」といった意見や、吹奏楽部であれば必要な楽器、小学校においては、図書室に「このような本があったら皆が喜ぶのではないか」というようなことを考えている。
- ただし、実施する内容については、自分たちの利益のみではなく、皆のためになることを考えてもらい具体的に決まるものである。地域の皆のためにどのようなものが望ましいかを考える過程を重視したいと思っている。そしてその結果、考えてもらったものについて知事が支援を行うことになる。
(委員)
- 各チームは大会に参加する前に、その夢のプランをたてるのか。
(文振課)
- ある程度考えていただいた後、それを受けて、実際に優勝したチームで話し合いの場を設けることを検討している。
(部長)
- 知事は自身の経験を踏まえ、上毛かるたの県大会で優勝することが地域のヒーローとなるとの思いを持っているが、最近、上毛かるたを空で言えない子供たちが増えていることに対して危機感を持ち、何らかの対策を講じるべきではないかとの指摘をされた。
- 担当からの提案として、「知事がみんなの夢を叶えます」と述べたのは、県大会で優勝することがヒーローとなり、より多くの人々のヒーローとなることで考えたものである。
- 単純に賞金を提供するというアイデアも存在したが、教育の観点から現実的ではなかった。そのため、「みんなのために」という言い方をしているが、優勝したチームが実際に欲しいものが手に入れられるようなことができないかというものである。
(委員)
- 3位ぐらいまでいれたらどうか。
(部長)
- まずは優勝チームにこの施策を実施させていただき、その効果をみて、非常に良いものであれば、ここの部分を膨らます、または、親子大会の方が親世代も含めた参加意欲や気運の醸成につながる可能性があるためこちらを増やす、なども考えられる。しかし、まずは令和7年度においてこの施策を実施して考えたい。
(委員)
- 賞金だけではなく、「ヒーロー」というものを考えると、広報活動が考えられる。例えば、県大会自体の番組や配信を行うことにより、露出をさらに増やすという考え方も有効であると思われる。
- また、「バズるぞ」というタイトルが挙げられており、どのように話題を提供するかが重要である。この点については、県内の番組や配信を通じて県外の視聴者にも届けることが可能である。その結果、他の県にも関心を持ってもらえる機会が増えると考えられる。
- 広報面での取り組みについて、現状はどのようになっているのか。
(委員)
- 上毛かるたが行われなくなった原因として、育成会の弱体化が挙げられる。また、根本的な原因として学校で上毛かるたが扱われていないことがある。つまり、育成会や学童クラブに任せきりになっており、学校教育の中で取り組みが行われていない。実際、大学での授業で、なぜ小中学校で上毛かるたを学習していないのかと、改めて思う。
- さらに、上毛かるたの本質を理解しないまま、ただ言葉を覚えることに専念している状況が見受けられる。そのため、県教委はしっかりと内容を伝える必要がある。
- また、文化振興課をはじめ何種類も副読本を作っているにもかかわらず、ほとんどが学校教育で使われていない状況に対して、県教委は何をしているのかという疑問が残る。
(委員)
- 私も育成会において審判員を務めているが、県大会と地区大会のレベル差は非常に大きいと感じている。地域の公民館でゆっくりと準備を進めて地区大会で優勝しても、県大会では歯が立たないのが現実である。
- このプロジェクトでは地域の子供たちへのサポートが十分に行き届かないのではないか。学校での取り組みを進めることが良い。地域での支援には限界があると感じている。
(委員)
- 私が学生時代には、マスメディアと地域のコミュニティしかいる場所がなく、そこでの評価や価値観を重視していた。地域の中にいるとその土地の価値あるものでも当たり前に思えてしまうことが多い。しかし、今の小学生たちはSNSやインターネットに多く接している。上毛かるたをはじめとする地域特有の文化や財産について、どれほど面白く、価値があるものであるかということを、インターネットに触れていることで逆輸入的発想で客観的に気づくことができる世代だと思う。
- たとえば、ひろゆき氏が温泉を楽しんでいる姿を見て群馬が温泉で有名であることを理解するように、群馬の上毛かるたをわかりやすくパッケージングすることが重要である。100万円の賞金はもちろんのこと、独特な賞品として、例えば、受賞時には通常のメダルではなく、SNSでもバズるような何か独特なアイデアが含まれているようなとても大きなかるたの盾がもらえるなどといった提案も考えられる。
- 自分の住んでいる地域の魅力や文化を客観的に評価する機会にもなると思うので、SNSなどでもインプレッションが集まるような景品を授与する、というのは若い世代の興味関心を得るきっかけのひとつになるのではないか。
(委員)
- 「みんなの夢を叶えますプロジェクト」というのは、ユニークな取り組みだと思うが、叶えて終わりではなく、何か具体的にそれを次にフィードバックする等事前にプログラムした方が良いのではないか。
(部長)
- これを実際どのようなプログラムで最後まで実施していくか全部描ききれてないため、皆様のご意見を参考にしながら良いものにしていければと思う。
【温泉文化ユネスコ無形文化遺産登録推進】
(委員)
- 温泉の無形文化遺産に向けた取り組みについて、群馬県ができることもあるが文化庁のプロセスと関連することが多いと思われる。その進捗状況について教えて欲しい。
(文振課)
- ユネスコの無形文化遺産登録については、ユネスコに申請を行うのは国であり、関係する省庁として文化庁等が存在する。文化庁とは、温泉文化の文化財としての位置づけ等について随時意見交換を行っている。
- 一方で、知事の会というものが存在し、群馬県をはじめとする各道府県でも、この取り組みに賛同する県があり、関係する温泉関連団体とも連携を図っている。主に温泉文化の機運醸成に取り組んでおり、県民のみならず国民全体にこの取り組みを知ってもらい、盛り上げることで、国全体でのムーブメントを引き起こすことを目指している。
(委員)
- 無形文化遺産については、山・鉾・屋台行事のように特定の祭りが選ばれるパターンと、和食文化全体のようなパターンが存在すると考えられる。温泉文化が無形文化遺産として認定される場合、日本の温泉文化全体がその価値となるのか、あるいは特定の温泉などが入るのか。
(文振課)
- 個別の温泉地、例えば草津温泉や別府温泉などではなく、日本全体の温泉文化をユネスコに登録して欲しいと取り組みを進めているところである。
- 文化庁には無形文化財の制度があり、現在、書道や華道が既に登録されているため、温泉文化についてもまずは無形文化財として登録して欲しいと考えている。
- そのためには、わざや担い手をしっかりと特定する必要があるとのことで、現在その点について文化庁と相談を進めているところである。
(委員)
- 温泉文化のユネスコ無形文化遺産登録に関して、群馬県が力を入れていることについて触れたい。群馬県は全国の温泉地のリーダーとして、このような活動を行っており、令和7年度にも計画していることに対して、心から敬意を表する。
- 昨年度のインバウンド消費額は8兆円を超えており、国の政策としては、いかに地域に行って消費を促進するかのコンテンツ造成に取り組んでおり、令和7年度も観光庁や国土交通省をはじめとする様々な省庁が補助予算を付けている。この中で、温泉文化がユネスコに登録された場合、和食を楽しむフーディーズによる高価格な消費のように、温泉地や温泉宿でも同様に世界各地からの旅行者による高価格な消費が見込まれている。
- このような背景を踏まえると、群馬県の取り組みは全国において先駆的であるが、ユネスコ登録に向けては一層の盛り上がりが必要であると考えている。特に、国民全体への裾野の広がりがなかなか見られない。
- 草津温泉や四万温泉、水上温泉などの温泉地においては、多くの方々が盛り上がっている様子を感じる。しかし、群馬県民全体の温泉文化のユネスコ登録に向けた機運醸成のようなものは存在するのか。もし、群馬県民の機運が見られないのであれば、温泉文化フォーラムなどの場で県民に参加を促すような呼びかけを行い、群馬県が盛り上がることによって、日本全国の国民も盛り上がりを見せる流れが生まれることができたら素晴らしい。
(委員)
- 温泉文化、ONSEN Culture in Japanは、世界遺産、世界の記憶と並ぶユネスコ三大遺産事業のもう一つのタイプ、無形文化遺産になりうるのではないかという原点にこだわることにたどり着く。その際、無形文化遺産にはジャンルがあり、「社会的慣習」に当てはまるのではないかと考えている。「社会的慣習」はかなり大きなジャンルである。しかし、日本の文化財保護体系とユネスコの無形文化遺産との間には若干のずれがあると考えざるをえない。「社会的慣習」はユネスコでは重視されるが、日本の文化財保護体系においては、まだ、それほど重点が置かれていない。「社会的慣習」としてなぜ登録可能なのかということを議論してきた。フィンランドのサウナ文化はフィンランド唯一の無形文化遺産だが、その担い手は550万のフィンランド国民全員であると述べており、フィンランド国民のまさに固有の文化であり、社会的慣習である。この点を私たちはしっかりと認識しておく必要がある。「温泉いいね」では済まない。
- 「フィンランドのサウナ文化、SAUNA Culture in Finland」と共に参考になるのは、和食の無形文化遺産登録である。実際、登録当時、和食は文化財保護法の枠組みにはなかった。その後の文化財保護法の改正に伴い食文化というジャンルが生まれてきたということがある。
- 登録運動において気を付けなくてはならないことが、もう一つある。ある業界の利益になるということでは通らない。ただ、登録後に、関係する業界がどう使うかは自由である。
- ここでも参考となるのは和食で、日本人の食文化全体を登録したと思われているが、実は四季折々の季節、自然の移ろいとの関係の中で、「おせち」のような季節感あふれる料理を日本人は食してきた。それが日本の和食ということで登録された理由である。しかし、今それよりはるかに広い範囲で和食を打ち出している。登録の前提として、温泉文化は全国民的な文化、社会的慣習だという共通理解をしっかりと作っていかないと、なかなか登録の壁は突破できない。
- そこで、遅ればせながら、一年ほどかけて、温泉文化ユネスコ登録の要望書という署名運動を進めている。これまでは温泉関係者で集めていたが、実際に使う側の人々、温泉に入ることで心身を癒し日常を回復してきた人々に署名集めの重心を移し始めている。恥ずかしいことだが、我々も、やっと、それに気づいたところだ。温泉は使う人、熱いお湯に入って日常を回復する習慣を持つ人々があって初めて価値が出るものであり、皆さんにもぜひとも署名運動に協力していただきたい。群馬の温泉登録ではない。全国民の社会的慣習としての温泉文化ユネスコ無形文化遺産登録である。そうした運動を全国民的に展開できるかどうかが重要である。ここが第2のポイント。
- いわば東京都民や大阪府民が「温泉文化は我々の社会的慣習、固有の文化だ」という意識を持って行動してくださるような運動にしたい。ここにどのように私たちが関わっていけるかが大きな課題である。
(委員)
- 私も温泉が大好きで、ぜひ推進してもらいたい。「ぐんま温泉街道」のイベントの一環として四万温泉と万座温泉のイベントを実施したが、様々な問題がある。特に、地方の温泉地では担い手が急速に減少している。
- 地域ごとに異なる事情があるものの、マナーの観点から混浴についても課題がある。四万温泉では公衆衛生上の問題も懸念されており、足湯に変更するなど世界標準にあわせた際に、元の文化をなくしてしまう恐れがある。日本の温泉文化が最高であると思ったのは、温泉を浴衣を着て歩くことを含めて、すべてが温泉文化であるからだ。
- このまま温泉文化を守っていくためには、温泉宿の担い手が高齢化しており、有名な温泉地でも人手が不足してきている。そのため、それを維持することはかなり至難の技だが、なんとか進めていただきたいと思う。
(委員)
- 温泉文化が日本固有の文化であったとしても、ユネスコが手を出さなくても維持できるのなら、無形文化遺産登録は必要ない。
- 温泉文化は、実は危機的な状況にあるから、ユネスコの力を借りてでも日本国内でそれを保全し振興し続ける体系をしっかり作ることが求められている。実際、温泉地の担い手の減少は凄まじく、現在、外国籍従業員の方々によってかろうじて保たれているほどだ。
- 台湾の方は温泉を大日本帝国の唯一の良い点であると評価され、受け入れていただいている。しかし、その他の国の方々は、あんな熱いものになぜ入るのか、衣服を脱ぎ、さらには知らない人と一緒に入るなんて理解できないと言われる。衣服を脱ぎ、熱い湯に、皆で入る。三つの大きな壁がある。その壁こそが日本固有の文化である。これを世界標準とどう合わせていくかも重要な課題である。ご一緒に考えていただきたい。
(4)群馬県民会館について
(委員)
- これは非常に難しい問題であり、全国的に同様の議論がある。こういう施設は大切だと思う層と、自分には関係ないと考えている層が分かれていることが大きな課題だと思う。
- 県として、この施設の公共的な意義をどこに置くのか。使う・使わないではなく、施設があることの幅広い意義を打ち立てていかないと、なかなか理解を得られないのではないか。
(委員)
- 地方での公演を行う際には、1,000席では狭く、2,000席程度のホールでコンサートをやりたいというアーティストや子ども向けテレビ番組の企画等としての需要はあると思う。
- ただ、県内には同規模の高崎芸術劇場や伊勢崎市文化会館など実施できる施設はある。
- 県として県庁所在地である前橋に足を運んでもらうきっかけになるという意味で、県民会館を存続させる価値があるのかをたくさん議論していく必要がある。
- あらゆる方法で価値を作ることはできると思うが、しかし、それが50億円に値するかは別途議論が必要だと思う。
(委員)
- 県民会館の存在自体が県民にとって大事なものだということ。その存在をどう残していくのかがこれまでの議論である。
- 文化を育て、文化を醸成するというのはすぐできない。歴史をつないでいくということを頭に入れながら、私としては存続という思いを持っている一人である。色々な意見を聞く必要があるし、県として、県民会館の理念を伝えていく必要がある。
(委員)
- この手の文化施設はハード面だけで成り立つものではなく、ハードとそれを動かしていく機関や組織とを一体で考えなければならないところがある。
- とはいえ、ハードの問題に特化して考えると、文化会館は、3つの事業で成り立っている。1つは主催事業(館が主催)で、公共の利益に資する事業として行政が主体的に実施する価値のある事業である。
- 2つ目は貸館事業で、二種類あり、うち一つは、プロのアーティストが借りて興行的な公演を行うパターンともう一つは県民が自分たちの文化活動の発表するために利用するものである。この3つの事業がうまく連携して運営されていれば、県民会館の主旨としても、経営的にも、十分に成り立っていくはずだが、現状、厳しい状況である。
- 貸館事業のうち興行的なものは、高崎芸術劇場が主要な役割を担ってしまっている。主催事業は、事業団はじめ指定管理者が意義のある事業ができていたのかというのは少し議論になってくる。加えて、群馬県が誇る主催事業の中核を担っているのは群馬交響楽団だと思う。その群馬交響楽団は群馬県、あるいは高崎市の歴史の事情によって、高崎芸術劇場で活動している。
- 残る事業は「県民の発表の場」としての役割だが、どの程度ニーズがあるのか、また改修することで県民の文化活動の発表の拠点としての役割を担い続けることができるのか、慎重に考えなければならない論点になる。
- 県民会館を改修する・しないに関わらず、群馬県の文化振興を推進していくためには、県民の文化活動のための拠点を無くしてしまうという考え方はあり得ない。何らかの形の拠点の確保は必要である。
- その拠点のあり方は議論の余地があると思うが、県民のための文化活動の拠点を県として用意するのであれば、単なる活動の場の提供としてだけではなく、「聖地」という表現は大げさかもしれないが何らかの意味でのシンボルとしての役割を、こうした文化的拠点は担いうるということを考慮する必要があると考える。
(委員)
- アンケートをそのまま受け取る訳にはいかないと思っている。県としてどういう風にしたいかという理念が大事。
- 改修工事50億円とあるが、どういう活用をしていくかも踏まえた金額で考えなければならないので、投資額としては60億、70億といった判断が必要になってくると思う。
- 何が残るかを考えたときに、もし県民の発表の場であるならば、主催事業や貸館事業ではなく、発表の場として最低限の部分を改修するという方法(2,000席ホールは改修しない等)もあるのではないか。
(委員)
- 県民会館なので、県民がいかに利用しやすいかに重きを置いて検討していければよいのではないか。
- この超高齢社会で、県民会館利用者は高齢者が多くなってくるかと思うので、高齢者が使いやすいための改修を行えば、施設としての必要性がでてくるのではないか。
(委員)
- 文化事業を発表する場として考えても、県民会館のある前橋は東京からのアクセスが悪い。高崎には高崎芸術劇場もできている。また、高齢化の問題や、車や公共交通機関でのアクセスが悪いということもある。今後のことを考えると、県民会館はある程度役割が終わったのではないか。
(委員)
- 広域自治体である県は、基礎自治体である市町村ができないことを補完するのが一番大きな役割(補完性の原理)。現在でも、県立の美術館や博物館はそう機能しており、運営経費や多額の改修費用の支出を県民は納得している。あの規模とレベルの美術館や博物館を市町村は持てないからだ。
- 一方、県民会館のケースを考えると、50年前には、各市町村が県民会館規模のホールを整備することができず、高崎市民の強力な運動で出来た群馬音楽センター以外には類似施設はなかった。そこで、群馬音楽センターと対になる形で、前橋側に県民会館が造られた。さらに、その後、県は、西毛地域に、みかぼみらい館・かぶら文化ホールを整備し、他方で、伊勢崎市・太田市・館林市は、自分の力で類似規模のホールを持つようになった。前橋市も、市民文化会館を建設した。
- 比較的大きな基礎自治体がみな「県民会館」的な施設を持ち、西毛地域に2つの県立施設が建ったことで、県民会館は、「補完性原理」に立った、その本来の役割を終えたと言えるかもしれない。もしも県民会館を廃止すると言うなら、古くなって改修費用がかさみ県は負担できないという理由ではなく、県立施設としての役割は終えたという論理でないと説得力がない。その議論が一番大切。
- ただ、資料を見たときに、利根・沼田、吾妻地域にはそれにふさわしいものがない。施設を作るのか、人材や事業でテコ入れするのかの議論が必要だが、バックアップしなければならないことは確か。
- 前橋市や高崎市は中核市であり、そこを補完する必要性は低い。
- 注目したいのは、みかぼみらい館の経緯。県が建てたものだが、藤岡市が取得した。県と基礎自治体の関係において模範的な移譲例ではないか。
- 極端な意見かもしれないが、県民会館も前橋(市民)が必要と考えるなら、県は無償譲渡してもいいのではないか。それなら論理が通る。
(委員)
- 個人的には、思い入れがあるので無くなると寂しい。
- ただ、あちこちに良いホールができている。なぜ県民会館が使われないかといえば、音響、響きの問題がある。合唱、声楽をやっても音が響かない。合唱コンクールを県民会館でやっても、全然響かないので困ってしまい、県民会館ではやりたくないということがある。
- ぐんま新人演奏会について、県教育文化事業団と一緒にやっているため、以前は県民会館を使っていた。そのため、県民会館の大ホールで歌えることがステータスだと考える声楽家達が多いが、もっと音響が良いところが望ましいということで、最近は藤岡市のみかぼみらい館で開催している。響きがよく、演奏しやすい。
- 県民会館で50億円の改修を行っても、音響が改善されるのかといったら無理ではないかと思う。(大規模改修のうち)音響関係では、小手先じゃないが、少し良くなるという改修しか入っていなかった。
- 県民会館が無くなるのは残念だが、無くなったとしても、こういった文化施設は必要なので、未来志向で考えていく必要がある。高崎には高崎芸術劇場がある。合唱関係、声楽における発表の場として何が必要かといったら、大ホールではなく、小ホール、中ホールが必要である。前橋テルサもなくなり、前橋市内のホールが前橋市民文化会館のみとなるので、小ホール、中ホールが大切ではないかと思う。
- 50億円をどう使うのかが論点になってくる。
(委員)
- 今後どうなっていくかを考えると、文化活動の多様化は間違いない。県の文化行政は、若い人の文化活動にリーチできていない。新しい文化活動の方向性を汲み取って考えていく、多様なニーズにあった拠点をつくる未来志向の考え方はありえる。
- 文化ホールとは違うが、仙台市にせんだいメディアテークがある。図書館やスタジオ、ギャラリー等の複合施設で、しっかりとした理念を持ち、様々な機能を組み合わせながら運用している施設である。様々な県民の文化活動の重要な拠点になるかと思う。
- 運営の方法についても柔軟な考え方もある。秋田の場合、県と市が共同で文化ホールを作っている。運営の方法についても、新しい時代に柔軟に対応できるよう、方向性を色々考えていくことはできるのではないか。
(委員)
- 改修するにしてもしないにしても、熱意をもって取り組んでいる人・組織が不足していると感じている。小さいライブハウスでも、熱意をもって企画をする人がいる。連日の企画や貸館はもちろん、例えば、2,000席ホールに少ししか観客が来なくてもチャレンジしてみようとか、文化活動はそういったところから新しい芽がでてくる。県の施設だからこそ、利益がでないことでも長期的な文化発展のためのチャレンジもできるなど、そういった両方の視点で軸に取り組める人・組織が必要である。どのように改修するか、どんなビジョンで存続させるかというところにはそれが影響してくると思う。再スタートにあたっては、人・組織の配置が重要だと思う。
(委員)
- 文化施設は範囲が広い。美術館・博物館系統、ホール、メッセ機能、映像・メディア部分、ギャラリー機能がある。県がどういう施設を今後持たなければいけないのか、整理したほうが良い。
- 例えば、美術館・博物館は当面県立施設として運営する必要があるし、県民もそれを望んでいる。一方、ギャラリー機能は、高崎シティギャラリーや藤岡のみかぼみらい館のギャラリー施設は見事で、他の市町村もそれなりの施設を持ち始めている。また、各市町村の美術館は、本来の美術館機能以上にギャラリー的機能を発揮しているように思われる。県がギャラリー機能を持つ必要性は低い。
5 会議資料
- 次第 (PDF:53KB)
- 資料ア 群馬県文化審議会について (PDF:82KB)
- 資料イ 群馬県文化審議会 部会委員案 (PDF:75KB)
- 資料ウ 令和7年度文化振興関連主要事業について(現在準備中です)
- 資料エ 群馬県民会館について (PDF:1.3MB)