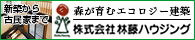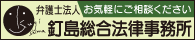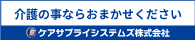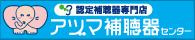本文
1.すこやかな妊娠と出産のために
(1)妊娠中の日常生活
妊娠中の母体には、おなかの赤ちゃんの発育が進むにつれて様々な変化が起こってきます。特に妊娠11週(3か月)頃までと妊娠28週(8か月)以降は、からだの調子が変化しやすい時期なので、仕事の仕方や、休息の方法(例えば家事や仕事の合間に、少しの時間でも横になって休むなど)、食事のとり方などに十分注意しましょう。 普段より一層健康に気をつけ、出血、破水、おなかの強い張りや痛み、 胎動の減少を感じたら、すぐに医療機関を受診しましょう。
(2)健康診査や専門家の保健指導を受けましょう
妊娠中は、特に気がかりなことがなくても、妊婦健康診査を受けて、胎児の育ち具合や、自身の健康状態(血圧、尿など)をみてもらいましょう。市町村では、健診費用に対する助成が行われています。
※妊婦健診等に関する厚生労働省のリーフレット<外部リンク>
健康で無事な出産を迎えるためには、日常生活、栄養、環境その他いろいろなことに気を配る必要があります。医師、歯科医師、助産師、保健師、歯科衛生士、管理栄養士などの指導を積極的に受け、妊娠、出産に関して悩みや不安があるとき又は家庭、職場でストレスがあるときなどは遠慮せずに相談しましょう。母親学級、両親学級でも役に立つ情報を提供しています。
出産前後に帰省する(里帰り出産など)場合は、できるだけ早期に分娩施設に連絡するとともに、住所地と帰省地の市区町村の母子保健担当に手続きなどを相談しましょう。
※妊婦健康診査をきっかけに、 下記のような妊娠中の異常 (病気) が見つかることがあります。
流産
妊娠22週未満に妊娠が終了してしまう状態です。性器出血や下腹部痛などの症状が起こります。 妊娠初期の流産は特に原因がなくても、 妊娠の約10~15%に起こるとされています。2回以上流産を繰り返す場合は、 検査や治療が必要な場合があります。
貧血
妊娠中は血が薄まって貧血になりやすいとされています。 出産に備え、鉄分を多く含む食事を取りましょう。ひどい場合には、治療が必要になります。
切迫早産
正常な時期(妊娠37週以降) より早くお産になる可能性がある状態です。下腹部痛、性器出血、前期破水などの症状が起こります。安静や内服などの指示が出されます。
妊娠糖尿病
妊娠中は、それまで指摘されていなくても糖尿病のような状態になり、 食事療法や血糖管理が必要となることがあります。
妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)
高血圧がみられる状態です。尿蛋白や頭痛等の症状を伴うことがあります。 急に症状が悪化することがあり、「強い頭痛がつづく」「目がちかちかする」といった症状がある場合などは要注意です。
前置胎盤
胎盤の位置が正常より低く、子宮の出口をふさいでいる場合をいいます。 大出血を起こすことがあります。 出産時には帝王切開が必要になります。
常位胎盤早期剥離
赤ちゃんに酸素や栄養を供給する胎盤が、出産前に子宮からはがれて(剥離)しまう状態です。赤ちゃんは酸素不足になるため、早急な分娩が必要になることがあります。主な症状は腹痛と性器出血ですが、胎動を感じにくくなることもあります。
(3)妊娠中の歯・口腔の健康管理
妊娠したら早めに歯科受診をし、必要な治療は安定期に
妊娠中は、女性ホルモンの急激な増加による口腔環境の変化や、「つわり」による歯磨き困難などによってむし歯や歯周病になりやすく、自身が初期症状に気づきにくいことも多いです。 安心して出産に臨むためにも、早めに歯科受診をし、むし歯や歯周病予防を心がけましょう。必要があれば妊娠安定期(概ね4~8か月)に歯科治療を行いましょう。
歯周病を予防して、健康で安心な出産を迎えましょう!
歯周病を放置したまま出産すると早産や低体重で出生する可能性が高くなると言われています。また、糖尿病などの生活習慣病と歯周病との関連も明らかとなってきました。
自分自身で行う毎日の歯磨きなどのセルフケアと、歯科医師・歯科衛生士によるアドバイスや専門的な歯面清掃などのプロフェッショナルケアを受け、歯周病を予防しましょう。
(4)たばこ・お酒の害から赤ちゃんを守りましょう
妊娠中の喫煙は、切迫早産、前期破水、常位胎盤早期剥離のリスクを高め、胎児の発育に悪影響を与えます。
妊婦や赤ちゃんのそばでの喫煙は、乳幼児突然死症候群(SIDS)と関係することが知られています。妊婦自身の禁煙はもちろんのこと、お父さんなど周囲の人も、妊婦や赤ちゃんのそばで喫煙してはいけません。
出産後に喫煙を再開してしまうお母さんもいます。出産後もお母さん自身やお子さんのために、たばこは控えましょう。
また、妊娠中の飲酒は、胎盤を通じてアルコールが胎児の血液に流れ込み、胎児の発育(特に脳)に悪影響を与えます。授乳期に飲酒すると、母乳にアルコールが含まれ、赤ちゃんに飲酒させることになってしまいます。
妊娠中は、全期間を通じて飲酒をやめましょう。出産後も授乳中は飲酒を控えましょう。今が生活習慣を変えるチャンスです!赤ちゃんにとって、たばこ・アルコールは、危険です。
(5)妊娠中の感染症予防について
妊娠中は、免疫力が低下して感染症にかかりやすくなっています。妊娠中は赤ちゃんへの影響も考えて有効な薬が使えないことがあります。日頃から手洗い、うがいなど感染予防に努めましょう。
何らかの微生物(細菌、ウイルスなど)がお母さんから赤ちゃんに感染し、まれに赤ちゃんに影響が起きることがあります。妊婦健康診査では、感染症の有無を調べることができるものもあり、治療を受けることで赤ちゃんへの感染を防ぐことができるものもあるのできちんと受診しましょう。
妊婦健康診査で調べる感染症
- 風疹ウイルス:お母さんが妊娠中に初めて風疹ウイルスに感染した場合、 赤ちゃんに胎内感染して、聴力障害、視力障害、先天性心疾患などの症状(先天性風疹症候群)を起こすことがあります。
- B型肝炎ウイルス:赤ちゃんに感染しても多くは無症状ですが、まれに乳児期 に重い肝炎を起こすことがあ ります。将来、肝炎、肝硬変、肝 がんになることもあります。 ヒト免疫不全ウイルス (HIV) 赤ちゃんに感染して、進行するとエイズ(後天性免疫不全症候群)を発症します。
- 性器クラミジア:赤ちゃんに結膜炎や肺炎を起こすことがあります。
- C型肝炎ウイルス: 赤ちゃんに感染しても多くは無症状ですが、将来、肝炎、 肝硬変、肝がんになることも あります。
- 梅毒:赤ちゃんの神経や骨などに異常をきたす先天梅毒を起こすことがあります。
- ヒトT細胞白血病ウイルス-1型 (HTLV-1): 赤ちゃんに感染しても多くは無症状です。一部の人が、ATL(白血病の一種、中高年以降)やHAM(神経疾患)を発症します。
妊娠中に心がけたい感染症対策
風疹ウイルス、サイトメガロウイルス、B型肝炎ウイルス、トキソプラズマなどの微生物 は、妊娠中、分娩中、または産後に、お母さんから赤ちゃんに感染して、赤ちゃんに病気を 起こすことがあります。 感染予防対策について、正しい知識を身につけておくことが大切です。
1.妊娠中は家族、産後は自分にワクチンで予防しましょう!
風疹、麻疹、水痘、おたふくかぜは、ワクチンで予防できます。(注1)ただし、妊娠 中はワクチンを接種できません。特に風疹は、妊娠中に感染すると、胎児に先天性風疹症候群を起こすことがあります。妊婦健診で、風疹抗体を持っていない、あるいは抗体の値が低い(注2.注3)場合は、同居の家族に麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)を 接種してもらいましょう。(麻疹は流早産の可能性があります)
注1:妊娠中でもインフルエンザ不活化ワクチンは安全かつ有効とされています
注2:HI法で16倍以下、EIA法で8IU/ml未満
注3:妊娠中の麻疹、水痘、おたふくかぜの感染の赤ちゃんへの影響はまだ分かっていません。妊娠前や産後に抗体を検査し、抗体を持っていない、または抗体の値が低いときは、ワクチンを接種することで感染を予防できます
2. 手をよく洗いましょう!
手洗いは感染予防に重要です。特に、食事の前にしっかり洗いましょう。 調理時に生肉を扱う時、ガーデニングをする時、動物(猫など)の糞を処理する時などは、使い捨て手袋を着けるか、その後、丁寧に手を洗いましょう。
3. 体液に注意!
尿、だ液、体液などには感染の原因となる微生物が含まれることがあります。 ご自分のお子さんのおむつでも使い捨ての手袋を着けて処理するか、その後で、丁寧 に手を洗いましょう。また、家族でも歯ブラシ等は共有せず、食べ物の口移しはやめましょう。
4. しっかり加熱したものを食べましょう!
生肉(火を十分に通していない肉)、生ハム、サラミ、加熱していないチーズなどは 感染の原因となる微生物が含まれることがあります。妊娠中は食べないようにしましょう。生野菜はしっかり洗いましょう。
5.人ごみは避けましょう!
風疹、インフルエンザなどの飛沫で感染する病気が流行している時は、人ごみは避け、 外出時にはマスクを着用しましょう。 子どもはいろいろな感染症にかかりやすく、子どもを介して感染する病気もあります。 特に熱や発疹のある子どもには注意しましょう。
※こども家庭庁ホームページ「妊娠と感染症」<外部リンク>
※国立感染症研究所ホームページ「母子感染」<外部リンク>
※赤ちゃんとお母さんの感染予防対策(日本産科婦人科学会等:PDF:64KB)
(6)妊娠・出産・授乳中の薬の使用について
妊娠中や授乳中の薬の使用については、必ず医師、歯科医師、薬剤師等に相談しましょう。自分の考えで薬の使用を中止したり、用法、用量を変えたりすると危険な場合があるので、医師から指示された用量、用法を守り適切に使用しましょう。
※ 妊娠と薬(厚生労働省)<外部リンク>
「妊娠と薬情報センター」において、妊娠中の薬の使用に関するカウンセリングが受けられます。 申し込み方法は以下のホームページをご覧ください。
※ 妊娠と薬情報センター(国立成育医療研究センター)<外部リンク>
(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)のWebサイトから、個別の医薬品の添付文書を検索することができます。
※(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)<外部リンク>
子宮収縮薬などの出産時に使用される医薬品についても、その必要性、効果、副作用などについて医師から十分な説明を受けましょう。
(7)無痛分娩について
経膣分娩の際、麻酔薬を使用し、陣痛の痛みを和らげる方法です。無痛分娩を検討される方は、各医療機関の診療体制をよく理解した上で、担当医と相談し、分娩の方法を選びましょう。
※全国無痛分娩施設検索(無痛分娩関係学会・団体連絡協議会)<外部リンク>
(8)妊娠中の夫・パートナーの役割
妊婦の心身の安定には、夫や家族など周囲の理解や協力が必要です。妻をいたわり、ねぎらい、家事を積極的に行いましょう。妻の妊娠期間の約10か月は、妻本人や夫・パートナーにとっても「親」として育っていく大切な準備期間です。この時期に、ふたりにとってこどもとはどんな存在か、親になるとはどういうことなのかなど、じっくり話し合ってみましょう。また、お産の時や産後の育児で夫がどのような役割を持つのか、妊娠中からよく話しあい、準備しておきましょう。
(9)RSウイルス感染症対策について
新生児や乳児に感染しやすいRSウイルスによる上気道感染の予防として、妊娠後期にお母さんにワクチンを接種して、生まれた赤ちゃんの感染症を予防したり、重症化をふせいだりすることもできます。2026年4月1日から定期接種となりました。詳しくは医療機関にご相談ください。
(10)妊娠・出産に伴う心身の変化
妊娠期から育児期は、ホルモンバランスや身体の変化、生活スタイルの変化などにより、誰でも心身が不安定になりやすい時期です。どんなことでもひとりで悩まず、周りの人や医療機関、母子健康手帳を交付した市町村の母子保健担当窓口などに話してみましょう。
特に、出産後に気持ちが落ち込んだり、涙もろくなったり、不安になったりすることがあり、多くの場合は一時的なものと言われていますが、気持ちの落ち込みや焦り、育児に対する不安などが2週間以上続く場合もあります。
産後うつは、産後のお母さんの10∼15%に起こるとされています。出産後は、お母さんは赤ちゃんの世話に追われ、自分の心や体の異常については後回しにしがちです。また、お父さんや周囲の方も赤ちゃんが最優先で、お母さんの変化を見過ごしがちです。妊娠中や出産後に不安を感じたり、産後うつかもしれない、と思ったときは、ひとりで悩まず医師、助産師、保健師、こども家庭センター等に相談し、産後ケア等の利用を検討しましょう。 産後ケアではお母さんの心身のケアや育児のサポート、授乳の支援等を行っています。 対象や実施方法、費用等は各市町村により異なります。詳しくは、市町村母子保健担当窓口にお問い合わせください。
また、妊娠中や出産時に異常があった場合は、出産後も引き続き治療や受診が必要な場合があります。経過が順調と思われるときでも、医師の診察を受けましょう。
(11)妊娠・子育て中や困ったときの相談窓口 一覧
妊娠・子育て中の不安や悩みなどを相談できる窓口を紹介します。どんなこともひとりで悩まず、相談してみましょう。
もしもの時の相談窓口
流産・死産を経験された方へ
お母さんがどんなに気をつけていても、流産・死産が起きてしまうことがあります。流産・死産や、子どもとの死別は、親近者との死別の中でも特に悲しみが強いといわれています。おつらい気持ちが少しでも軽くなるよう、専門職や、同じ経験をされたお母さん方とお話ができる相談窓口があります。詳しくは、県ホームページをご覧ください。
予期しない妊娠をされた方へ
群馬県助産師会では、予期せぬ妊娠で悩んでいる方の相談を電話・メール・LINEで受けつけています。相談は無料です。
※群馬県ホームページ「『ぐんま女性の健康・妊娠SOS相談』電話相談をご利用ください」
(12)出生前検査について
お腹の赤ちゃんの検査には、妊婦健診で全員が受ける検査(普通の超音波検査)と、希望した人だけが受ける「出生前検査」があります。出生前検査は、検査についての情報を充分に得て、検査結果がわかった後のことについてもよく考えた上で、受けるか受けないかを決めることが大切です。
また、出生前検査は、どの医療機関でも受けられるわけではありません。皆さんの気持ちに寄り添いながら、適切に検査やその後のサポートができる、認証医療機関が定められています。まずは、かかりつけの産婦人科、市町村母子保健担当窓口等へ相談しましょう。
(13)妊娠中の性生活
むやみに避ける必要はありませんが、妊娠初期や妊娠後期の性交渉は出血や子宮収縮の原因となりやすいので控えましょう。おなかを圧迫しないことも大切です。おなかの張りがあったら中止し、出血や休んでもおさまらない張りが起きたら、速やかに産科医療機関を受診しましょう。
また、細菌やウイルスがお母さんから赤ちゃんに感染して、赤ちゃんに病気を起こすことがあります。尿、だ液、体液などには感染の原因となる細菌やウイルスが含まれることがあります。妊娠中の性生活ではコンドームを着用し、オーラルセックスは避けましょう。