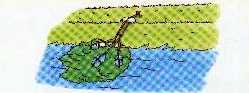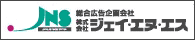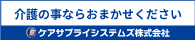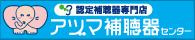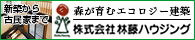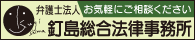本文
水防
治水事業は、計画的に進められていますが、事業が完成するまでには、長い年月と莫大な費用がかかります。
また、治水事業が完了しても計画規模を超える雨が降ることもありうるため、水害の発生が完全になくなるわけではありません。
そこで、水害による被害を最小限に食い止めるため、水防活動が必要となります。水防活動は、一般的には市町村ごとに設置される水防団(複数の市町村で広域水防団として設置されたり、消防団が兼務している場合もある)が行いますが、一般の住民も協力して行うこともあります。
群馬県では、水防活動が効率的に行われるよう、毎年水防協議会に諮って「群馬県水防計画」を作成し、関係機関の活動、連結体制、各河川の重要水防箇所などを定めています。
また、毎年5月を水防月間として水防に対する意識の高揚に努めています。
水防管理団体
31団体
水防活動事例

令和元年10月(台風第19号) 月ノ輪工法 明和町
主な水防工法の紹介
シート張り工法
水の流れで堤防が削り取られたり、水が漏れたりしないように、防水シート(マット・畳・むしろ)を張って堤防を守ります。

月の輪工法
堤防の裏側に水が漏れ出したとき、半円形に土のうを積んで、河川の水位と漏水口との水位差を縮めて圧力を弱め、水漏れが拡大するのを防ぎます。

積土のう工法
堤防の上に土のうを積み上げて、水が堤防を越えるのを防ぐ方法です。水防工法の基本ともいえる工法で、一つの土のうには30~50キログラムの土砂が詰められ、さまざまな工法にも使用されています。
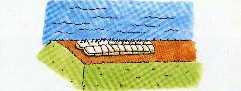
木流し工法
水の流れが急なとき、枝葉のよく繁った木を川に流し、水の勢いをゆるやかにして堤防が洗掘されるのを防ぎます。